今日は、社労士の仕事のなかでも相談顧問にぐっと焦点を当ててお話しします。読み終わるころには、なぜ社労士にとって相談顧問が重要で、しかも自信を持って積極的に取り組むべきなのかその理由が腑に落ちるはずです。
手続き業務の比率が高くて、なんとなく忙しさばかりが増えていく、そんな感覚になることはありませんか?私もまさにそのひとりでした。
これから開業する方や、駆け出しの方ならなおさら、“先が見えにくい不安”を抱くことがあると思います。そんなとき、一つの選択肢になるのが「相談顧問」です。これは、私自身が経験して実感したことでもあります。
社労士の仕事は大きく2種類に分けられる
一般的な社労士事務所が、企業と顧問契約を結んで担う主な業務は、大きく2つに分かれます。
この2つの業務を簡単に説明すると一般的に以下のようになります。
労働集約型業務
まずは、社労士がよく引き受ける3つの仕事を「労働集約型」と呼んでいます。具体的には、労働・社会保険の手続き、給与計算、それから助成金の申請などです。
このあたりは“手を動かしてなんぼ”の仕事です。書類を作ったり数字を計算したりと、実務的な作業が中心になります。
頭脳活用型業務
一方で、人事制度を作ったり、就業規則を直したり、こういう仕事は、同じ顧問業務でもまったく性質が違います。
書類をひたすら処理するのとは違って、メインは「考えること」。頭の中で組み立てて、答えを導き出す仕事なんですよね。
相談顧問とは何か、そしてなぜ需要があるのか
相談顧問とは、手続きや給与計算などの労働集約型業務は含めず、頭脳労働のなかでも相談・指導業務(=労働問題の相談に回答・指導)に特化した顧問契約を指します。
なぜこの形態が求められるのか。理由はシンプルで、労働集約型業務は慣れれば社内でも対応可能である一方、労働法・労務管理は専門性が高く、社内だけでの対応が難しいからです。
「手続き等は社内で行うが、法判断や運用の肝は専門家に相談したい」というニーズにフィットするのが相談顧問です。
実際、全国社会保険労務士会連合会が公表した『2024年度社労士実態調査』によると、顧客からの需要について “相談業務” が5年前と比較して“増加傾向にある”と回答されています。こうした調査結果から見ても、相談業務を必要とする企業は今後も増えていく可能性が高いと感じています。
「遠慮しすぎ」になっていませんか?
なぜ相談顧問に踏み出せないのか原因はさまざまですが、私の肌感覚では、経営者に対する過度な遠慮や萎縮が背景にあるように思います。社労士の多くは会社員経験から独立するケースが多いせいか、
「社長に意見するのは申し訳ない」と感じてしまうことがあります。
私も同じでした。でも実際に相談業務を始めると、「もっと早く相談しておけばよかった」「相談して良かった」と言われることが本当に多いんです。
企業の現場には、その会社ならではの事情があります。それを整理して最適な方向性を示すのは、社労士だからこそできる役割です。
相談顧問の需要はある
「社長」と一口に言っても、本当にいろんなタイプがいます。年齢も性別も違うし、バックグラウンドもバラバラ。その中には、労務管理にあまり興味がない社長もいます。
でも一方で、労務管理を会社の基盤としてちゃんと大事に考えていて、「ここは専門家の力を借りたい」と思っている社長も間違いなくいるんです。私たちが探すべき相手は、まさにこのタイプの社長です。
経営に長けた社長でも、労務管理や労働法のプロではありません。もちろん経験で勝る部分はあるでしょうが、体系的な知識や最新の動向に関しては、社労士の方がずっと強い。だからこそ自信を持って「自分の専門性を提供していい」と言えるんです。
相談顧問のメリットと開業当初の注意点
相談顧問の魅力をあらためて整理すると、大きく二つあります。
ただし注意点もあります。開業したばかりだと仕事が少なくて不安になり、「とりあえず手続きや給与計算も受けよう」となりがちです。もちろん経験にも収入にもつながるので、一概に悪いとは言えません。
ただ、たとえば給与計算を一度受けてしまうと、締め日から支給日までの“動かせない繁忙期”が毎月必ずやってきます。ここに縛られると、新しい相談案件に力を割けなくなってしまうんです。
だからこそ、「どこまでやるか」「どこはやらないか」という線引きを、できるだけ早いうちに決めておくことをおすすめします。将来の立ち位置を考えたうえで選んでいくことが大切なんですよね。
私の事務所の実情
開業当初の私は、まさに手続き顧問を増やしまくったタイプでした。仕事があるのはありがたいけれど、徐々に追われるような感覚になっていきました。書類が山積みになり、月末は毎回、心の余裕がほとんどありませんでした。
このままじゃいけないと思い、相談顧問中心へ切り替えていきました。ありがたいことに今では、相談顧問:3割、手続き顧問:7割、という状態になり、相談顧問の比率をもう少し増やす計画です。
相談顧問を依頼してくださる企業は、私の場合、人事体制が整った100名規模の会社が多く、「手続きは自社で、判断は外部の専門家に」というニーズが合うのだと思います。
相談が続く中で、感謝の言葉をいただく場面が増えました。これは何より励みになりますし、私自身の意識も変わりました。
AIやシステムで手続き業務が効率化される流れは、今後ますます加速していくはずです。だからこそ、人が頭を使って判断する仕事の価値はより高まっていくと感じています。
まとめ
社労士の仕事は、大きく以下の二つに分けられます。
多くの社労士事務所は前者を中心にしていますが、実は相談顧問のような頭脳活用型には確かな需要があります。私自身、手続き業務でキャパオーバーになり、相談顧問へ比重を移したことで働き方が大きく変わりました。
もし心のどこかで「相談の仕事もやってみたい」と感じているなら、一歩踏み出してみるのも悪くないと思います。
自分の専門性をどう活かすかは、人によって違います。でも「相談」という働き方が合う方は、想像以上に多いと感じています。無理なく挑戦できる範囲から、少しずつ始めてみてもいいのではないでしょうか。
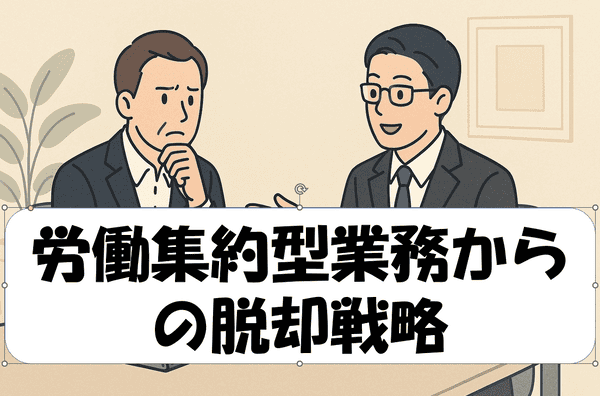


コメント