「会社員を続けるべきか、それとも独立すべきか…」キャリアの大きな岐路に立ったとき、迷うのは当然です。
この記事では、会社員として働く方が士業などで独立開業を考える際に、どのように判断すればよいかについて社労士を例に解説します。人はそれぞれタイプが違いますので、「どの選択が正しいか」は一つではありません。
読み終えていただければ、独立に進むべきか、それとも今の会社員としての道を続けるのが合っているのか。ご自身の中で、少しは整理がつくんじゃないかと思います。
人生の大事な岐路に立つと、どうしても迷いますよね。だからこそ、判断材料は多いほどいいはずです。この記事がその材料のひとつになれば嬉しいです。
会社員の利点と欠点
独立を考える前に、まず「会社員にはどんな良さと難しさがあるのか」。ここを整理するところから始めてみます。
会社員の利点は、やっぱり毎月の安定した収入です。これは本当に大きい。生活のベースが整うだけで、精神的なゆとりも違ってきます。
それに、よほどのことがない限り解雇されにくいという点もあります。日本では雇用の保護が強いので、多少ミスをしたからといってすぐに職を失う、というケースはかなり少ないです。
福利厚生や研修制度が整っている会社も多く、働きながらスキルアップできるのも見逃せません。さらに、大企業や専門性の高い組織に勤めていると、個人ではまず関われないような大きなプロジェクトに携われることもあります。こうした経験は一生ものです。
ただ、その一方で欠点もあります。希望した仕事に就けないこともあれば、やりがいや目的を見失ってしまう時期が訪れることもあります。仕事は続くのに、気持ちが置いていかれるような、そんな感覚になる方もいます。
給与は出るので生活は安定するのですが、長く続けるうちに「このままでいいのかな…」と考え込んでしまうケースも珍しくありません。
もう一つ意識しておきたいのは、どんな企業でも、経営環境が変われば業績が悪化する可能性があるということです。これはどの会社でも起こり得ます。再就職の際に武器になるスキルがなければ、転職に苦労する場合もあります。
かつては「良い大学から大企業に就職できれば一生安泰」という時代もありましたが、今はそうではありません。企業の安定も、以前ほど当たり前ではなくなってきました。
こうした背景を踏まえた上で、会社員か独立かを考えていく必要があります。
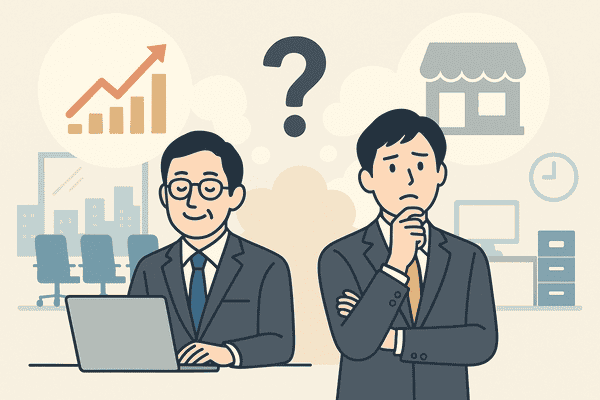
あなたの会社は安定しているか?
ここまで、会社員という働き方のメリットとデメリットについてお話してきました。そして次に考えたいのが、「あなたの勤めている会社は安定しているのか、それとも不安定なのか」という点です。
もし会社の経営が不安定で、先行きが読めないような状況にあるなら、将来を見据えて別の働き方を検討する方もいます。ただ、社労士としての開業一本に絞る必要はありません。安定した会社へ転職するという選択肢も、同じくらい現実的です。社労士の開業が必ずしもバラ色とは限りませんから。
反対に、会社が安定していて、今後も安心して働ける環境である場合。そのときは、あなた自身のタイプに応じて判断が変わってきます。
この場合にまた今度はあなた自身の人間のタイプ、これを三つに分けて考えていく必要があります。(あくまで個人的な意見ですので、最終的にはご自身の環境や性格によって判断してください)
安定志向タイプ
まず、あなたが会社員という働き方に向いていて、「このまま何年、何十年と続けても構わない」と思える場合。このケースでは社労士としての開業は必ずしも急いで選ぶ必要はありません。
社労士として開業しても、もちろんうまくいく方もいますが、思ったより難しい場面に出会うこともあります。準備や継続的な努力が欠かせません。
実際、開業登録をすると所属する社労士会から毎月会報が届くのですが、その「会員異動」の欄には新規開業者だけでなく、毎月数名の廃業者の情報も掲載されています。つまり、開業の裏側では、別の働き方へシフトされる方も一定数いらっしゃるということです。
会社員という働き方は、安定性・継続性という意味で非常に大きな価値があります。もしそこに安心感があるなら、そのキャリアを丁寧に積み重ねていくのも立派な道だと思います。
挑戦情熱タイプ
中には、会社員としての仕事にも十分適性があり、今の会社も安定しているのに、「もっと自分で動きたい」「事業として挑戦したい」と感じるタイプの方もいます。こういう方は、仕事に対して非常にエネルギッシュで、何事にも主体的に取り組み、成果を出すことが得意なタイプです。
このタイプの人は、会社員としても結果を出しやすい一方で、「自分の裁量で動ける環境」への憧れが強い傾向があります。そういった意味では、このタイプの方は 独立して働くスタイルと相性が良いといえるかもしれません。
もちろん、開業にはリスクもあります。ただ、準備を怠らず、計画的に行動できる人ほど、そのリスクをうまく乗り越えて成長につなげていくことがあります。挑戦そのものが原動力になるようなタイプですね。
また、独立は「会社員か、独立か」の二択ではありません。今の会社で働きながら、ゆっくり準備していくという方法もあります。
脱サラしたほうがいいタイプ
もう一つのパターンとして、組織がどうしても性に合わないという方もいます。仕事の進め方や評価のされ方に違和感を覚えやすかったり、環境との相性がうまくいかない場合もあるでしょう。
そうしたときは、一度働き方そのものを見直すのも一つの方向性です。
もちろん独立には責任も伴いますが、自分のスタイルに合わせて働けるというのは大きな魅力です。前向きに取り組める環境が整えば、意欲が高まる方もいます。
ただし、独立を考えるときは、情報収集や資金計画、経験の棚卸しなど、少しずつ準備していくことが大切です。急ぐ必要はありません。
私自身の経験
ここまで、会社が安定しているか・していないか、そして会社員に向いているか・向いていないかという大きな分類でお話ししてきました。それでは私の場合はどうだったのかというと、タイプで言えば 「組織(会社)に向かない部分がある」 と同時に、「挑戦してみたいという強い気持ち」 も持っていました。
組織に向かない大きな理由のひとつは、派閥争いでした。エンジニアとして働いていた頃は、そうした政治的な動きとはほとんど無縁で、仕事に集中できていました。ところが、人事部に異動してからは状況が一変。親会社に媚を売る人が出世したり、派閥争いの勝ち負けで評価が決まるような場面を何度も目にしました。
本来の実力や成果ではなく、「うまく立ち回った人」が高く評価されるという環境に心底嫌気がさしたのです。もちろん、それが組織の現実だと割り切る道もあったでしょう。でも、私にはどうしても耐えられませんでした。
一方で、そうした環境から抜け出し、自分の裁量で仕事を進めたい、事業を自分で動かしたいという前向きな思いもありました。この「組織に馴染めない面」と「挑戦への意欲」という二つの要素が、社労士として独立開業を決断する大きなきっかけになりました。
この2つの想いが重なったとき、私は“独立”を選びました。そして今振り返っても、この選択は私にとって正しかったと感じています。
まとめ
社労士として独立開業するか、それとも会社員を続けるか、その答えは人それぞれです。
会社員には安定収入や身分の保証といった大きなメリットがありますが、倒産リスクや、やりがいを感じにくい環境に置かれるといったデメリットも存在します。
自分が「安定志向なのか」「挑戦したいのか」「どうしても組織に合わないのか」、性格や価値観を振り返ることで、どの道を選ぶべきかが見えてきます。
大切なのは、自分自身が納得できる選択をすること。開業にはリスクもチャンスもあります。あなたにとって後悔のない決断をしていただきたいと思います。

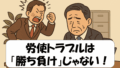

コメント