この記事では、社労士の仕事の中でも特に安定した収入源となる「顧問契約」について、私の経験も交えながら率直にお話ししていきます。
開業社労士として14年の経験を持つ私自身の体験に基づき、顧問契約の種類や相場、そして顧客との信頼関係を築き契約を継続させるための秘訣、さらには避けて通れない解約との向き合い方についても紹介します。
社労士として安定した基盤を築きたい方や、顧問契約の仕組みについて知りたい方にとって、ヒントになる情報をまとめました。
社労士のサービスは単発(スポット契約)と顧問契約
私が仕事をしていると、初めて会った方から「社労士さんって、具体的にどんな契約があるんですか?」と聞かれることがよくあります。
実はそこまで複雑ではなく、ざっくり分けると2つのタイプがあります。ひとつは、必要なときだけ依頼される“単発(スポット)”の仕事。就業規則の作成だったり、助成金の申請だったり、いわゆる「この案件だけお願いします」というものです。
もうひとつが、毎月お付き合いが続く顧問契約。企業の労務担当のような立ち位置で、手続きのサポートや相談対応を続けていく形です。顧問税理士さんや顧問弁護士さんのイメージが近いと思います。
この記事では、この「顧問契約」について、私なりの経験も踏まえて深掘りしていきます。
顧問契約の形態と相場
顧問契約の形態は事務所ごとに自由ですが、実際に多いのは次のパターンです。
では、実際にどのくらいの顧問料が目安になるのかを見てみます。
顧問料の一例(通常の顧問契約:基本手続き+相談)
以下は、私自身の経験や、周囲の事務所の料金を見てきた中で感じただいたいこの金額のイメージです。
| 社員数 | 月額顧問料 | 社員数 | 月額顧問料 |
|---|---|---|---|
| 4人以下 | 20,000円 | 60~69人 | 60,000円 |
| 5~9人 | 25,000円 | 70~79人 | 70,000円 |
| 10~19人 | 30,000円 | 80~89人 | 80,000円 |
| 20~29人 | 35,000円 | 90~99人 | 90,000円 |
| 30~49人 | 40,000円 | 100~119人 | 100,000円 |
| 50~59人 | 50,000円 | 120人以上 | 別途協議 |
顧問料の一例(相談顧問)
次に相談顧問の場合の報酬例です。こちらも私の実務経験や周囲の事務所の傾向を踏まえたイメージです。
| 社員数 | 月額相談顧問料 | 社員数 | 月額相談顧問料 |
|---|---|---|---|
| 4人以下 | 10,000円 | 60~69人 | 30,000円 |
| 5~9人 | 12,500円 | 70~79人 | 35,000円 |
| 10~19人 | 15,000円 | 80~89人 | 40,000円 |
| 20~29人 | 17,500円 | 90~99人 | 45,000円 |
| 30~49人 | 20,000円 | 100~119人 | 50,000円 |
| 50~59人 | 25,000円 | 120人以上 | 別途協議 |
ここで大事なのは、契約をどこまで増やせるかは、事務所の規模や体制によって全然違う、ということです。
私の事務所の場合、通常顧問として対応できるのは社員80名くらいまでが限界だなと感じています。というのも、100名を超えると入退社の届出や社会保険の手続き、年度更新や算定が一気に増えて、実際にパート職員の勤務時間を延ばしてしのいだことがあるからです。
実際、小規模事務所では業務量が急に増えると負担が大きくなりがちで、他の顧問先にも影響が生じかねません。なので、それ以上の規模の会社については「相談顧問」として契約するようにしています。
要は、顧問料の金額をどうするかを考える前に、「うちの事務所なら何人規模までなら無理なく通常顧問を受けられるか」という線引きをしておいた方がいい、ということですね。ここをあいまいにしたまま走り出すと、「仕事量が多すぎて回らない」という状況に陥る可能性があります。
地域・業種により差はありますが、顧問契約は長期に続くケースが多いため、最初から無理のない受けを決めておくことが、結果的に安定経営につながると実感しています。
顧問契約を続かせるコツ
私の経験上、顧問契約は長期に継続するケースが多いです。一見すると顧問料の金額が重要に思えますが、実際には信頼関係が特に重視される傾向があります。私の経験上、顧問契約を長く続けてもらうために大事なのは以下のような点です。
ここでひとつ、私の経験を紹介します。ある会社が事業を縮小し、最終的に社長1名だけの体制になったことがありました。手続きも相談もほとんど無くなったため、普段は言わないのですが「顧問契約を継続されますか?」と社長に聞いたのです。
すると社長は、「人員整理のときに親身になって相談に乗ってもらったから、手続きがなくても続けたい」と答えてくださり、今でも契約は続いています。
この経験からも、顧問契約は“どれだけ手続きがあるか”より、“どれだけ信頼を築けたか”で継続が決まると実感しています。
「信頼関係をどう作って、どう続けるか」については、もう少し踏み込んで 独立しても顧客が途切れない人の共通点!信頼される関係づくりの秘訣 でもまとめています。
大切なのは「解約を恐れない」姿勢
契約書上では「更新停止は○ヶ月前告知」としている事務所が多いと思います。私も開業当初はそうしていて「3か月前までに連絡してください」というルールにしていました。でも今は契約条文を変えて、お互いいつでも解約できる形にしています。
理由はシンプルで、顧問契約って結局は信頼関係があってこそ続くものだからです。お互いに「もうやめたいな」と思っているのに、形だけのルールで縛って続けても良いことはありません。むしろ、解約は状況の変化に応じて起こり得るもので、双方にとって前向きな区切りになる場合もあります。
よくある解約理由はこの2つです。
私の事務所では、平日9〜18時、土日祝は休みを基本にしています。その範囲で顧問料に見合うサービスを誠実に提供する。これが私のスタンスです。それでも「より広い対応時間」「大幅な値下げ」と求められるなら、無理に引き止めない方が双方にとって健全です。
むしろ、サービス内容の範囲を大きく超える要望が続く場合よりも、信頼関係を築けるお客様と長くやり取りしていく方が、事務所にとっても安定しますし、気持ちよく仕事ができます。
顧問契約は“最初の線引き”が肝心
顧問契約は一度結ぶと長く続くものですが、その分「最初の取り決め」が曖昧だと後から不満やトラブルにつながりやすいです。
私自身も経験があります。例えば、以前「助成金申請も顧問料に含まれていると思っていた」と言われたことがありました。契約時に線引きをしていなかったために説明に時間がかかり、お互いに気まずい思いをしたのです。
それ以降は契約のときにきちんと線引きをするようにしていて、それだけで関係は驚くほどスムーズになりました。特に意識しているのは次の2点です。
まとめ
顧問契約は、性質上長く続くケースが比較的多い契約です。だからこそ大切なのは、日々の信頼の積み重ねと、最初のルールをきちんと決めて定期的に見直すこと。
そして、顧問契約が安定してくれば、新規営業に追われなくても事務所を維持できるようになります。顧問先との関係づくりにしっかり時間を割けるのは、社労士の大きな強みだと思います。
社労士として顧問契約を育てるうえで大切なのは、解約を恐れすぎないこと。むしろ信頼できる顧客と腰を据えて関係を深めていくことが、長期的に見ても事務所の安定と、自分自身の安心につながります。
【執筆】イタル(社会保険労務士)
開業14年の社会保険労務士。社労士開業や事務所運営について、実体験をもとに解説しています。
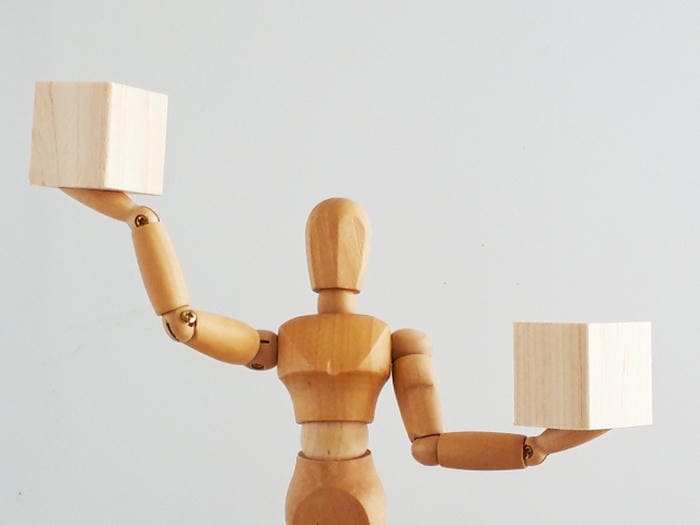


コメント