静寂を破るミルの音。手間をかけることで始まる「自分だけの時間」
キャンプ場の朝は早い。まだ他のテントが眠りに包まれている頃、私はシュラフから抜け出し、ひんやりとした外気の中に身を投じる。59歳という年齢のせいか、あるいはこの静寂を独り占めしたいという欲求のせいか、自然と目が覚めてしまうのだ。
まず最初に行うのは、コーヒーを淹れるための「儀式」だ。平日の朝、東京での生活では、豆からコーヒーを挽くなんて贅沢は到底できない。時間に追われ、インスタントやコーヒーメーカーで済ませるのが常だ。しかし、キャンプ場では時間が何よりも豊かにある。
小型の筒型ミルに豆を入れ、ゆっくりとハンドルを回す。ゴリゴリという振動が掌に伝わり、静まり返った森の中にその音だけが響く。ふわりと漂い始める、深く香ばしい香り。この香りを嗅いだ瞬間、私の脳は「今はもう、仕事のことは考えなくていいんだ」と、日常からの切り離しを完了させる。
お気に入りのピークワン・デタッチャブルストーブに火を灯し、「ゴーッ」という頼もしい燃焼音を聞きながらお湯が沸くのを待つ。お湯を注いだ瞬間、コーヒーの粉がぷっくりと膨らみ、きめ細やかな泡が立つ。その様子を見つめていると、これから淹れ上がる一杯への期待感とともに、自分の心の中のささくれが、ゆっくりと平らになっていくのを感じるのだ。
理想の情景。澄んだ空気とチタンカップが教えてくれる「今」という瞬間
私の理想とするコーヒーの情景は、派手なものである必要はない。朝もやに包まれた高原や、すぐそばを流れる清流のせせらぎ。そんな自然の音に包まれながら、スノーピークのローチェアに深く腰掛ける。これが私の特等席だ。
愛用しているのは、チタン製のダブルウォールマグ。軽量でありながら熱を逃がしにくく、口に運んだ時の金属のひんやりとした感触と、中身の温かさのコントラストが心地いい。
一口啜ると、温かい液体が喉を通り、体の中にじんわりと熱が広がっていく。その瞬間、私の意識は「今」という点に集中する。昨日、クライアントとの打ち合わせで感じた微かな不安や、自営業者として抱え続けている責任感。そんな、普段の私を縛り付けているあらゆる「重み」が、霧が晴れるように消えていく。
清流の音を聞きながら、ただカップを持って座っている。スマホを見ることも、誰かと話すこともない。ただ、コーヒーの味と、空気の冷たさと、目の前の緑の色だけを感じる。この「何もしない」という行為こそが、現代においてどれほど困難で、そしてどれほど贅沢なことかを、59歳になった今、切実に感じるのだ。
仕事の「眠気覚まし」ではなく、心の「豊かさ」を味わうために
平日の仕事中に飲むコーヒーと、キャンプ場の朝に飲む一杯。それは同じ飲み物でありながら、私にとっては全く別物だ。
事務所で飲むコーヒーは、いわば「戦うための道具」である。眠気を覚まし、思考をクリアにし、時には溜まったストレスやイライラを抑え込むためのもの。マイナスに振れそうな自分の状態を、なんとかプラスマイナスゼロに引き戻すために、半ば義務的に喉へ流し込んでいる側面がある。
しかし、キャンプ場の一杯は違う。そもそも気分が良い状態を、さらに高みへと連れて行ってくれる。何の不安も心配もなく、心からこのシチュエーションを楽しめる、純粋な「加点」のためのコーヒーだ。
効率を求め、一分一秒を惜しんで仕事をしている日常では、コーヒーを「味わう」ことすら忘れてしまっている。けれど、ここでは一杯のコーヒーを淹れるために15分以上の時間をかける。その無駄とも思える工程のなかにこそ、人間としての豊かさが宿っているのではないか。そう思えるだけで、私の心は驚くほど軽くなる。
59歳の「心の洗濯」。再び街へ戻り、日常を歩むための大切な儀式
私にとって、このキャンプ場での15分間は「心の洗濯」そのものだ。仕事のこと、自分自身の健康のこと、そして家族のこと。年齢を重ねるほどに責任は増し、考え出せばキリがないほど悩みは尽きないものだ。
日常の喧騒の中にいると、どうしても心に澱(おり)が溜まっていくのを感じる。だからこそ、定期的にすべてをリセットし、心を真っさらな状態に戻す作業が必要になる。
コーヒーを飲み終え、温かくなったマグカップを両手で包み込みながら、私は「よし、また明日から頑張ろう」という静かな活力を得る。それは決して、無理に自分を奮い立たせるようなものではない。もっと穏やかで、自然な、前向きな気持ちだ。
「何もしない、ただコーヒーを飲むだけの15分」
若い頃の私なら、この時間を「もったいない」と感じたかもしれない。もっと多くの場所を巡り、もっと効率的に動くことを選んだだろう。けれど、今の私にはわかる。この短い余白が、残りの膨大な日常を支えてくれているのだということが。
キャンプ場を後にし、車を走らせて街へ戻る。バックミラーに映るキャンプ場が遠ざかっても、私の心の中には、あの朝の静寂とコーヒーの香りが確かな手触りとして残っている。その感覚をお守りのように携えて、私は再び、自分の日常へと足を踏み出していく。
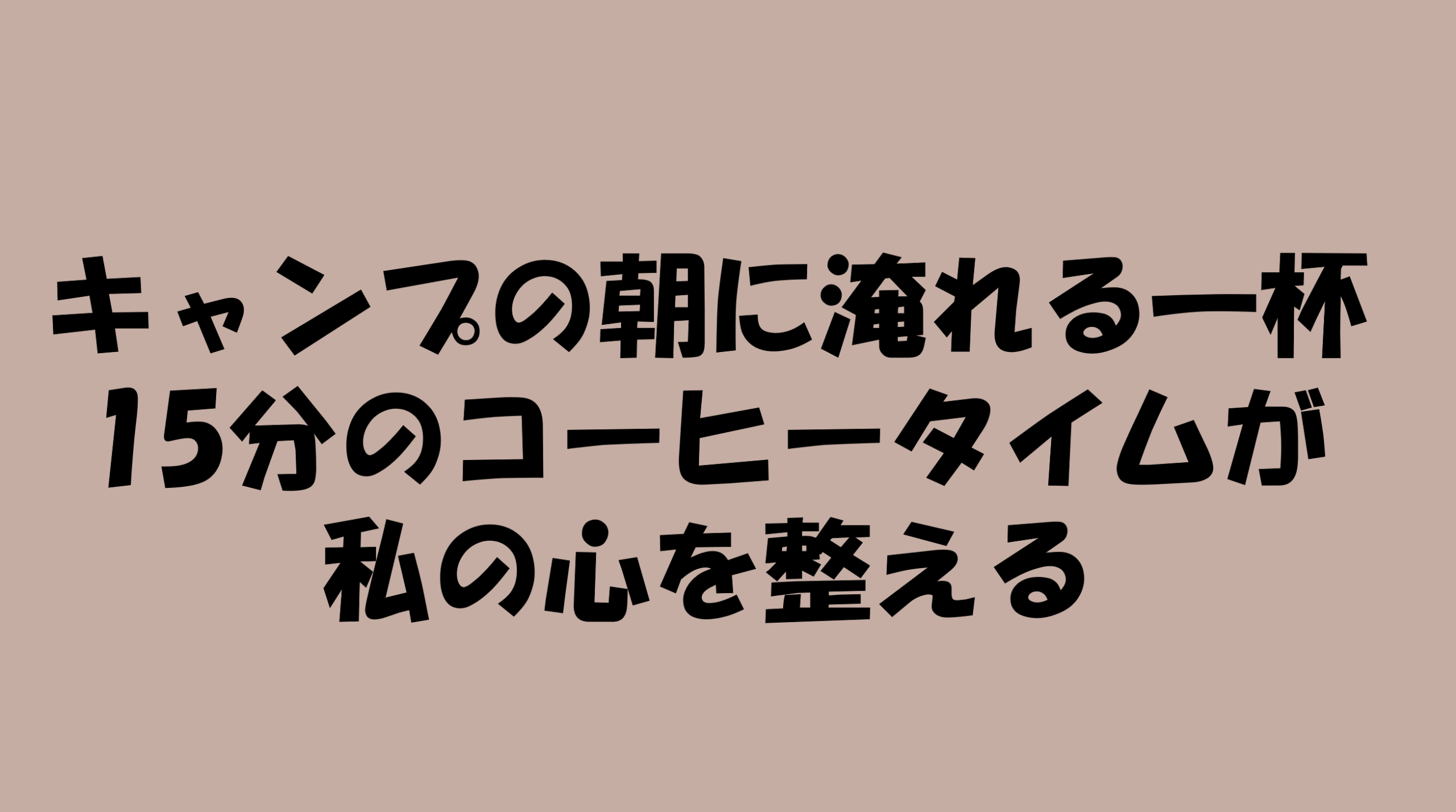


コメント