どこまでも続く地平線。ペダルを踏む足に伝わる「地球の丸さ」
59歳になった今、日々の仕事は効率と論理の連続だ。コンサルティングの現場では、いかに無駄を省き、最短距離で答えに辿り着くかが求められる。
しかし、ふと目を閉じると、今でも鮮やかに思い出す景色がある。17歳の夏、高校生だった私が、フェリーに自転車を積み込み、三週間かけて走り抜けた北海道の道だ。
当時はワンゲル部に所属していたこともあり、一人で野営をしながら進むことに抵抗はなかった。けれど、これは部活動ではなく、私個人のプライベートな旅だった。重いキャンプ道具を自転車に積み込み、誰に指示されるでもなく、自分の意志だけで行き先を決める。
漕ぎ出すたびに自転車がギシギシと悲鳴を上げても、ペダルを踏み込む太ももに伝わってくるのは、きついというよりも「自分の力だけで、前へ進んでいる」という心地よい抵抗感だった。
中標津にある開陽台に立った時の衝撃は、今でも肌が覚えている。そこから眺める景色は、360度のうち330度が地平線だった。行きのフェリーから見た海の水平線とは違う、緑の陸地が緩やかに弧を描き、空へと繋がっている。「地球は本当に丸いんだ」と、知識ではなく感覚として理解した瞬間だった。
知床峠を超えた時の達成感も格別だった。霧の中の峠を越え、目の前に現れた羅臼岳の力強さ。今思えば、ヒグマの恐怖も顧みずによくあんな場所を自転車で走り抜けたものだと思うが、あの頃の私には、そんな不安よりも「まだ見ぬ先へ、自分の足で辿り着きたい」という純粋なエネルギーが勝っていた。

百人浜で手渡された「幸せの貝」17歳の夏に触れた、旅の優しさと甘酸っぱさ
一人で走り続ける旅は、決して孤独なだけではなかった。道中、予期せぬ人の温かさに何度も救われた。
襟裳岬に近い百人浜に立ち寄った時のことだ。そこは「拾うと幸せになれる」と言われる、蝶の形をした「蝶々貝」が取れることで知られていた。そこで出会った、同じく旅行中だった同年代の女の子。彼女が偶然見つけたというその貝を、私にプレゼントしてくれたのだ。
彼女はその貝を私に渡すとき、マジックを取り出して「頑張ってね」と書いてくれた。大きな荷物を背負って自転車を漕いでいる少年の姿に、彼女なりにエールを送ってくれたのだろう。
59歳の今振り返れば、それは青春のほんのり甘酸っぱい一コマに過ぎないのかもしれない。けれど、当時の私にとって、その小さな白い貝は、この先何km続くかわからない道を走り切るための、何よりも眩しいお守りになった。
雨に降られ続けて、心が折れそうになった夜もあった。テントを張る気力もなく、役場の軒下で夜を明かそうとしていた私に、「宿直室を使いなさい」と声をかけてくれた職員さん。畳の上で眠れることのありがたさに、涙が出そうになった。
根室半島のキャンプ場でカニをごちそうしてくれた大学生や、日高でバーベキューに混ぜてくれた家族連れ。高校生が一人で自炊しながら旅をしているというだけで、皆が驚き、そして惜しみない親切を分けてくれた。あの旅で得たのは、絶景だけではなく、世界に対する「信頼」だったのだと思う。
「生きる」というシンプルな喜び。四つ葉牛乳と炊き立てのご飯
旅の間、私の生活は驚くほどシンプルだった。毎日、地元のAコープでその日の食材を買い、使い慣れたストーブでご飯を炊く。それだけのことなのに、キャンプ場で食べる食事は、震えるほどおいしかった。

横たわる相棒(自転車)と小さなテントだけが、この最果ての地で私を守ってくれる全てだった。
体を極限まで動かし、空腹を抱えて食べるという行為。そこには、今の飽食の時代や、便利な仕事の中では味わえない「生きていく本能」への感動があった。
特に、旅のエネルギー源として毎日欠かさず飲んでいた「四つ葉牛乳」の味は、私の概念を変えた。東京に戻ってからいつもの牛乳を飲んだとき、「なんだ、この水のような飲み物は」と驚愕したほどだ。濃厚で、命の味がする牛乳。それを喉に流し込むたびに、北海道の広大な大地そのものを体に取り込んでいるような気がした。
今の私は、何事も「意味」や「目的」で判断しがちだ。けれど、あの三週間、私はただ「パンを買い、テントを張り、米を炊き、眠る」という基本的な行動に、全神経を集中させていた。それこそが人間にとって最も贅沢で、誇らしい時間の使い方だったのではないかと、今になって強く感じる。
1日100kmの贅沢。弾丸旅行では味わえない「時間の使い方」を今の自分へ
当時は、自転車で移動できる距離なんて、一日せいぜい100km程度だった。バイクや車なら数時間で通り過ぎてしまう距離を、私は丸一日かけて、汗を流しながら進んだ。
日高地方の海岸線を走り、旅の終わりが近づくにつれて、胸の中に「帰りたくない」という寂しさがこみ上げてきたのを覚えている。あれほど不自由で、雨に打たれ、泥にまみれた旅だったのに、終わりが来るのが何よりも惜しかった。

59歳の今の私が、17歳のあの少年を見かけたら、こう声をかけてあげたい。 「君は今、人生で最高に贅沢な時間を過ごしているんだよ。大人になれば、こんなにまとまった休みは取れなくなる。効率を求めない旅が、どれほど君の心の根っこを作るか、楽しみにしておきなさい」
そして、あの夏に行く決断をしてくれた自分に、「本当によくやったね」と感謝を伝えたい。
今の私の生活は、相変わらず忙しい。けれど、仕事で行き詰まったときや、心がささくれ立ったとき、私はそっとあの北海道の風を思い出す。地平線の向こう側に沈む夕日。蝶々貝に書かれた「頑張ってね」の文字。そして、あの濃厚な牛乳の味。
便利さの影で見落としてしまいそうな「生きている実感」を、私はあの三週間の旅の中で、確かにこの手で掴み取っていたのだ。


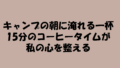
コメント