社労士の仕事って、つい「手続きが中心」と思われがちですよね。けれど実際の現場でいちばん勝負が決まるのは、社長や従業員からの相談にどう応えるか。ここに尽きます。
ここで言う「相談力」は、相談を受けたときにどう対応し、最適な解決へ導く力のこと。こちらから相談を持ちかける力でも、相談の持ち込み方でもありません。いわば相談に応じる力=相談対応力だと考えてください。
この相談力があるかどうかで、社長からの信頼のされ方は大きく変わります。信頼が積み上がれば声がかかりやすくなり、その積み重ねが結果として評価や報酬にも反映されていくというそんな流れです。
そして相談力は、一つの技だけで完結するものではありません。土台になっているのは「問題解決力」「コミュニケーション力」「経営支援」という三つの視点。これらが噛み合って初めて、本当に使える相談対応ができます。
では、この三つをどう伸ばしていくか。ここからは私自身の経験も交えながら、順番にお話ししていきます。
問題解決力を高める!社労士の相談力の第一歩
相談を受けたときにやってはいけないことがあります。それは表面的な質問にすぐ答えてしまうことです。
表面的な質問に即答するのではなく、「なぜその相談が出てきたのか?」という背景を丁寧に掘り下げることで、本質的な解決策が見えてきます。
雇用に関する相談のケース
「解雇について教えてほしいのですが」と相談を受けたとします。ここで「解雇は30日前に予告が必要です」なんて表面的に当たり前のことを答えるのではなく、大事なのは「なぜ解雇のことを質問したのか?」を聞くことなんです。
上記のように背景はいろいろ考えられます。もし人件費の問題なら、生産性を上げて残業時間を減らすとか、配置転換をするとか、別の道もあるわけです。つまり同じ「解雇について教えてほしい」でも、背景次第でアプローチ方法は全然違うんですよね。
就業規則作成のケース
「就業規則を作りたい」と相談を受けることもよくあります。ただ、その理由をよく聞いてみると、まったく違う対応が必要になることが多いんです。
同じ「就業規則を作りたい」という依頼でも、背景次第でアウトプットはまったく変わります。こうした違いを見抜いて、最適な提案ができるのが社労士の問題解決力だと思います。
ハラスメント相談のケース
最近特に増えているのが「ハラスメントにどう対応すべきか」という相談です。
要するに、法律的に問題がないかだけを答えて終わりでは不十分なんですよね。どうすれば同じ問題を繰り返さないか、その仕組みまで含めて提案できることこそ、社労士の役割であり価値だと感じます。
残業削減のケース
「社員の残業時間を減らしたい」というご相談は、本当によくいただきます。
だから残業の話は、「36協定を守りましょう」だけで片づきません。会社の体制や文化のところまで踏み込んで、打ち手を一緒に考えるのが大事なんです。
選択肢を提示する姿勢
また、相談を受けた場合に注意すべきなのは、解決策を一つだけ押し付けないことです。解雇・就業規則・ハラスメント・残業管理といったどんなテーマであっても、考えられる解決策は複数あります。
例えば3つくらい候補を出して「それぞれメリット・デメリットはこうです。そのうえで私のおすすめはこれですが、最終的には社長が決めてくださいね」と伝える。これだけで社長の納得感はまるで違います。「一緒に考えてくれてるな」と思ってもらえるんです。
コミュニケーション能力を磨く
どんなに知識があっても、話し方や聞き方が下手だと相談力は半減します。結局、相談は「会話」で進んでいくものだからです。大事なのは次の3つ。
これって一見当たり前なんですけど、やろうとすると意外と難しいんですよね。つい自分がしゃべりすぎたり、間を怖がって埋めてしまったり。私自身も最初はそうでした。
でも、ただ「声に強弱や緩急をつけよう」と意識するだけではなかなか身につきません。私の場合、効果的だったのは面談をボイスレコーダーで録音して後から聞き返すことでした。
面談では、事前に許可をいただいたうえでボイスレコーダーを使用し、自分の話し方を振り返るために録音していました。
例えば「えー」「あのー」といった口ぐせが多いとか、声が単調で一本調子になっているとか、逆に間を取らずに早口になってしまっているなど。
そうした癖を意識して直すために、私は改善点を紙に書き出して次の練習で意識するようにしました。「口ぐせを減らす」「大事なところでは必ず一拍置く」など、チェックリストのようにして練習を重ねると、少しずつ改善されていきます。
結局のところ、小さな工夫を積み重ねながら繰り返すことが、相談力につながるコミュニケーション改善の一番の近道だと思います。
社長の右腕として「従業員を巻き込む経営支援」
相談力を発揮すると、単に「制度を整える」だけでなく、社長が抱えている悩みを整理し、その解決策として「従業員を巻き込む経営」を提案できるようになります。
社長が一人で意思決定を背負い込まずに済む仕組みを作ることが、社労士にできる大きな支援です。
たとえば残業削減の相談では、単に36協定を説明するのではなく、従業員を交えた業務改善会議を設ける提案が有効。
またハラスメント問題なら、社長だけが判断するのではなく、ハラスメント防止委員会や相談窓口を設置したり社員研修を導入して「会社全体で改善に取り組む」形を作ることができます。
こうした具体的なサポートによって、社長は「一人で抱え込む必要がない」と実感でき、安心して意思決定ができるようになります。これこそが、相談力を発揮して初めてできる経営支援だと言えるでしょう。
まとめ
社労士に求められることは、問題解決力とコミュニケーション力、経営支援の視点を磨くことで、社長の右腕として選ばれる存在になることです。
そして相談力を高めるには、次の3つがポイントです。
この3つを実践できれば、単なる手続き屋ではなく、社長の右腕として信頼される社労士になれます。結果として評価につながることもあります。そう考えると、「相談力を磨く」というのは、キャリアにも年収にも直結する一番の近道なんです。


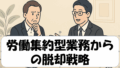
コメント