開業を考えると、多くの人が“まずは修行が必要だろう”と考えるのではないでしょうか。けれど実は、その常識を疑ってみると、思わぬ答えが見えてきます。
本記事では、修行にとらわれずに独立を成功させる考え方、そして他の社労士と差別化して顧客に選ばれるためのヒントを紹介します。
先輩の事務所での修行は必要か
社労士として独立するというのは、それなりに覚悟のいる選択です。資格を取っただけでは仕事が勝手に舞い込んでくるわけではありませんし、どこかのタイミングで「自分をどう売り出すか」を考える必要があります。結局のところ、お客さんがあなたを選ぶ理由がなければ、なかなか仕事にはつながりません。
とはいえ、すごく特別なスキルがなくても、開業して意外とうまくいってしまう人もいます。運なのか、人との縁なのか、そのあたりは説明がつかないこともあります。ただ、そういう人は本当に一握りで、多くの場合は何かしら工夫をしながら道を切り開いていくものです。
そこでよく聞かれるのが、「開業前に先輩社労士の事務所で修行した方がいいのか」という質問です。期間についても「何年くらい働けば安心ですか?」と相談を受けることがあります。
私の考えを先にお伝えしてしまうと、修行は“絶対に必要”というほどのものではないと思っています。むしろ、人によっては遠回りになってしまうこともあるのではないか、というのが率直なところです。
私自身も他事務所で働かずに開業しましたが、困ったら調べたり、周りに尋ねたりしながらなんとか形にしてきました。周囲を見ても、修行した人やしなかった人がいますが、成功の仕方に大差があるようには感じません。
先輩の真似をしないほうがいい理由
先輩の社労士事務所で働くというのは、言い換えれば「その人のやり方をなぞる」ことになります。良くも悪くも、そこで身につくのは“先輩の仕事のクセや価値観”です。
もちろん、真似から学べることはあります。ある程度慣れてくれば、先輩より効率的にこなせるようになることだってあるでしょう。でも、それは結局のところ 同じレーンを走っているだけ なんですよね。その間に置き去りにされがちなのが、自分の持っている色や強みです。
よく「朱に交われば赤くなる」と言いますが、環境の影響は想像以上に大きいです。事務所に長くいるほど、その事務所の考え方ややり方が“当たり前”になってしまい、気づけば、あなたならではの価値が埋もれてしまう可能性があります。
そうなると、お客様から見たときに「この人じゃなきゃいけない理由」が薄れてしまいますよね。だからこそ、「何年修行すればいいのか?」という質問は、私の中では少しズレているように感じます。
おそらく質問される方の本音は、「長くいるほど安心だけど、そんなに時間はかけたくない。結局どれくらいが妥当なの?」というところにあるのだと思います。
でも、私の答えは逆です。修行は必須ではないし、やるとしても長くいる必要はありません。
理由は単純で、長く居続けるほどその事務所のやり方にどっぷり浸かってしまうからです。それが悪いとは言いませんが、“あなたの型”が作りにくくなるのは確かです。
もちろん、「社労士事務所の空気感を一度経験しておきたい」という目的で短期間働くのはアリだと思います。ただし、その場合も 完全に染まりきってしまう前に外へ出ること が大事です。
修行なしで開業しても大丈夫な理由
「修行をせずにいきなり開業して、本当にやっていけるのか?」これは、多くの方が一度は感じる不安だと思います。ですが、私の経験から言えば、いきなり開業しても十分やっていけると思います。
社労士事務所での“修行”と聞くと、多くの方は次のような実務を思い浮かべるのではないでしょうか。
確かに、こうした実務は必要です。ただ、今の環境を考えると、これらを身につけるために、わざわざ長期間どこかに所属する必要はありません。
書類の書き方にしても、ネット上には記入例や解説が豊富にあります。困ったときは公式マニュアルや行政のQ&Aを確認すれば、大抵のことは解決します。
役所とのやり取りについても、コロナ以降は窓口へ行く機会が大きく減りました。ほとんどの手続きが電子申請で完結しますし、むしろ電子申請を使いこなせない方が不利になるくらいです。電話での問い合わせはありますが、それだけのために“修行”が必要だとは私は感じません。
書類作成や役所対応は、開業して仕事を受ける中で自然と覚えるものです。むしろ、誰かから教わるより、自分で調べたり、実際に手を動かしたりしながら覚えたほうが、身につきやすいこともあります。
もちろん、最初のうちは失敗することもあります。ただ、それで取り返しがつかなくなるような場面はほとんどありません。間違えたら直し、次に活かす。その積み重ねこそ、実務力になっていきます。
最低限の知識や準備は必要ですが、だからといって「修行をしなければ開業できない」という話ではありません。必要なことは、開業後の実践の中でいくらでも身につきます。
自分の強みで顧客に選ばれる方法
最後にもうひとつ大事なことがあります。「修行もしないで差別化なんてできるの? どうやって顧客に選ばれればいいの?」そんな不安に答えておきましょう。
結論はシンプルです。顧客の目線に立てばいいんです。
顧客が欲しいものを知る
社労士として独立する目的はただひとつ。「お客さんに選ばれること」ですよね。じゃあ、そのために何が必要なのか。実は、ここが意外と見落とされがちなんですが、まずは“お客さんが本当に求めているもの”を知ることなんです。
例えば、就業規則の作成依頼があったとします。そのまま規則を作ること自体はできますが、多くの場合「紙としての就業規則」が目的ではありません。
こうした質問を通じて、少しずつ“本音”が見えてきます。結局のところ、お客様が欲しいのは「規則そのもの」ではなく、会社を安心して運営できる状態です。つまり、「安心できる未来」を提供することが本質なんです。
あなたの経験と社労士業を結びつける
もうひとつ大事なのが、あなた自身の経験や個性です。これまでの人生で培ったもの、勉強してきたこと、得意なことなどなんでも構いません。
それを社労士の仕事と掛け合わせることで、“あなただけの商品” を作ることができます。そして、その商品を「顧客が欲しい」と思う形に加工して提示すれば、それが差別化になります。
例えば、私自身の話ですが、開業当初から「地域密着」を軸にしました。営業エリアを市内の限られた範囲だけに絞ったのですが、これが思った以上に効果的でした。
「すぐ来てくれる距離感」「顔が見える安心感」こうした“地域性”自体が付加価値になり、お客様にとっては選びやすい理由になるのです。特別なスキルがなくても取り組める差別化の方法として、とても有効でした。
先輩の真似には意味がない
上の流れを整理すると、必要なのは次の3つです。
- 目的:顧客に選ばれること
- 対策:顧客の気持ちを理解すること
- 手段:自分の強みを商品化し、提供すること
この中に、「先輩のやり方を忠実に真似する」という項目は特に含まれていません。もちろん、先輩の働き方から学べることはありますし、参考にできる部分もあると思います。ただし、“そのままコピーする”のは、結果的にあなたの個性を薄めてしまうことが多い。
先輩と同じ道を歩いてしまうと、どうしても “その他大勢” に埋もれやすく、自分ならではの価値を出しにくくなります。
だからこそ、「先輩と同じやり方」ではなく、「あなた自身の強みを軸にしたやり方」を選ぶ方が、結果的に顧客から選ばれる可能性が高くなると私は感じています。
断定というより、“実際にいろいろな開業者を見てきた経験から、そう思う” というニュアンスです。
まとめ
ここまで、開業にあたって“修行は必要なのか?”というテーマでお話ししてきました。
あらためてポイントを整理すると、次のようになります。
今回の内容は、私自身の経験や、周囲の開業者を見てきた中で感じたことをもとにしています。少なくとも私の実感としては、修行をしなくても十分にやっていけるということです。
結局のところ、開業後に問われるのは“自分の魅せ方”と“お客さんへの向き合い方”です。他人の型にはまる必要はありませんし、自分の強みを活かすほうが結果として選ばれやすくなります。
どういうスタイルで仕事をするかは、人それぞれです。ぜひ、自分らしい方法で道を切りひらいていってほしいと思います。
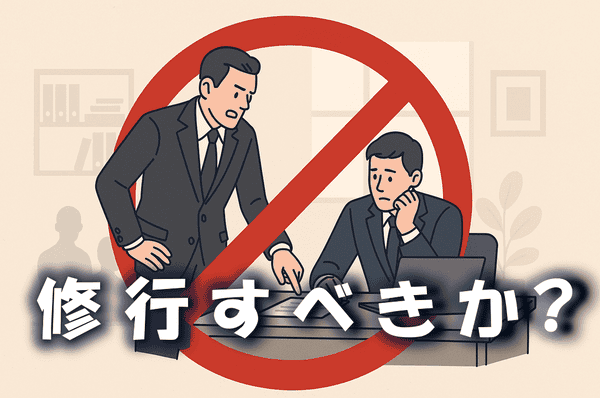


コメント