社労士試験に合格したものの、開業後に失敗してしまう人がいます。「資格は取ったのに仕事がない」「どうやって顧客を獲得すればいいかわからない」そんな声も珍しくありません。
なぜそのようなことになってしまうのでしょうか? この記事では、社労士として成功するために必要な要素と、開業後に直面しやすい課題について解説していきます。
社労士開業で失敗する人の特徴と対策
社労士試験に合格する人って、やっぱりコツコツ型が多いんですよね。日々の勉強を地道に積み重ねて、インプットとアウトプットを繰り返す。真面目で努力家の方が多いなという印象があります。
それに、深く考え込みすぎず、要点を広く押さえて効率よく知識をまとめていける人も、合格しやすい傾向にあるようです。
ただ、開業して実際に仕事を始めるとなると、話はちょっと変わってきます。必要とされる能力が、試験勉強とはまったく別の方向にあるんです。たとえば、お客さんと直接話をして、その中から課題を見つけて提案につなげる力。それから、YouTubeやブログ、メルマガ、LINEなんかを使って、自分の考えやサービスを発信していく力もすごく大事になってきます。
つまり、勉強中はインプットが中心だったのが、開業後は一気にアウトプット重視に変わるわけです。もちろん営業も含まれますけど、それだけじゃなくて、人とつながって信頼関係を築いたり、誰かに紹介してもらえるような動きをしたり。あるいは、困っている経営者がいると聞けば、自分から会いに行って話を聞く、みたいな姿勢が大切になってきます。
でも実際には、「いつか仕事が入ってくるだろう」と思って、ずっと勉強を続けてしまう人も少なくないんです。気持ちはすごくわかります。せっかく合格したわけだし、もっと知識を深めたいというのも当然です。
でも、残念ながら、勉強だけしていても食べていけるわけじゃない。仕事がないまま時間が過ぎてしまって、経験も積めず、自信もつかないまま、モヤモヤする…そんな悪循環に入ってしまうケースもあります。
開業後に必要なのは、「勉強→実践→フィードバック」という、行動を通じて成長していくスタイルなんじゃないかと思います。学ぶことは大事。でも、実際に体を動かして、現場で得られる経験から学ぶことのほうが、むしろ重要だったりします。
要するに、試験に向いているのはインプット型の人。でも、実務で成果を出せるのは、アウトプット型の人なんですよね。このギャップが、開業後に最初につまずくポイントなんじゃないかと感じています。
勉強は得意でも、人と話すのが苦手だったり、発信するのに抵抗があると、その壁を越えるのはなかなか大変です。だけど、そこを乗り越えた先に、ちゃんと成果が待っていることも、たくさん見てきました。
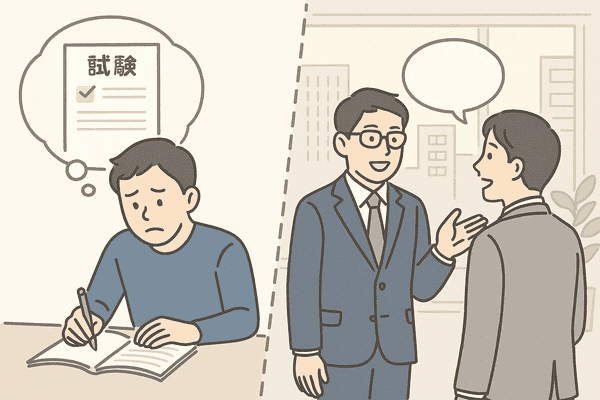
社労士の仕事の魅力と、開業後に待ち受ける2つのハードル
社労士って、すごく社会的に意味のある仕事だなと、やっていてつくづく感じます。いま日本は少子高齢化がどんどん進んでいて、働き手が減ってきているんですよね。これはもう避けようがない大きな流れです。
その影響で、法律が変わったり、社会保険の仕組みや労働環境、助成金制度なんかも次々に見直されています。特に、どこの企業でも「人が足りない…」という声は本当に多くなっています。
こうした背景の中で、昔ながらの雇用の仕組みや運用方法のままでは、人が定着しないという企業も増えてきました。実際に、「どうしたら辞めずに働いてくれるのか」と悩んでいる経営者の方は少なくありません。
そこに対して、社労士は就業規則を整えたり、人事制度を見直したり、助成金を活用した支援を提案したりと、いろんな角度から企業をサポートできる立場にあります。
それから、企業にとって一番大きなコストって、やっぱり人件費なんですよね。その次に大きいのが社会保険料です。介護保険も含めると、労使合計で給与総額の約3割前後に達することもあります(2025年時点・協会けんぽ東京支部の料率をもとにした概算)。この金額を改めて知って驚かれる経営者の方も少なくありません。
こういう部分をうまくコントロールして、無理なく企業が人に投資できるようにしていく。その支援ができるのも、社労士ならではの強みだと思います。
そんなわけで、社労士の役割ってこれからもっと求められていくはずなんですが、そこで2つほど、大きなハードルがあります。
1つ目のハードル:税理士との業務性質の違い
まず最初にぶつかるのが、社労士と税理士との「仕事の性質の違い」です。税理士って、会社を作ったら必ず発生する「確定申告」がありますよね。あれは本当に専門的な作業だし、社長が自分でやるにはハードルが高すぎる。だから、多くの経営者はごく自然に「税理士にお願いしよう」となります。
一方、社労士の仕事はというと、もちろん役立つ場面はたくさんあります。でも、「必ず社労士がいないと困る」という業務が少ないのが現実です。だからこそ、自分から「こういうこともできるんですよ」と伝えていく必要が出てきます。
といっても、ただ売り込むのではなくて、相手との会話の中で「それ、実は社労士がサポートできますよ」と自然に気づいてもらう。そんな営業スタイルが求められる資格なんです。いわば、“需要を作っていくタイプの資格”なんですよね。
具体的には、今の状況を丁寧に聞いて、「理想はどういう姿ですか?」「なぜそれが必要なんですか?」といった話をしながら、本当に必要なことを一緒に見つけていく。そして、そのうえで「こうすれば解決できますよ」と提案していく。
そんな“問題解決型の営業”ができるかどうかが、仕事を取れるかどうかの分かれ目になります。
税理士のように“やらなければならない業務”が少ないぶん、社労士は自分からアウトプットしていかないと、存在自体に気づいてもらえません。情報提供をしたり、相手に質問を投げかけながら、潜在的なニーズを引き出していく。
この「伝える力」や「気づかせる力」がなければ、なかなか仕事にはつながっていかないのが実際のところです。
2つ目のハードル:すでに社労士が入っている企業との競合
ここ最近、社労士の需要ってじわじわと高まってきていて、それ自体はすごく喜ばしいことなんですが、
その一方で、ある程度の規模の会社には、すでに別の社労士さんが入っているケースが増えてきているんですよね。
私が開業したのはもう14年ほど前なんですが、当時と比べると明らかに増えてます。「やっぱり、もう社労士さんがいるの?」って思うことが、正直なところ今では当たり前です。
そんな中で新しく顧客を獲得していくには、当然ですが「今の社労士から切り替えてもらう」ことが必要になりますよね。でも、そう簡単な話じゃない。いま担当している社労士さんに特に不満がない場合、わざわざ乗り換える理由がないわけです。
だからこそ、「今の社労士が手をつけていないところ」「見落としているポイント」をこちらから伝えて、気づいてもらう必要があるんです。ここでもやっぱり、会話が大事になってきます。
開業して仕事を取っていくには、試験合格とは真逆のスキル、つまり人と話して伝える力とか、自分の考えを外に向けて発信する力が必要になってくるんですよね。
このギャップは、けっこう大きいです。だから最初は戸惑う方も多いと思います。でも、そこを乗り越えて「ちゃんと伝える」「信頼を築く」ことができるようになると、やっぱり伸びていく人が多いなと感じています。
こうした“実務に必要な行動力や発信力”を軽視してしまうと、開業が失敗に終わる可能性も十分にあるのです。
まとめ
「人に会う」「発信する」ことを少しずつ始めていくのが失敗しないための第一歩です。試験に受かった努力は、ちゃんと開業後にも活かせます。あとはそれを、外に向けてどう使っていくかだけ。無理せず、自分のペースでできることから始めてみてください。
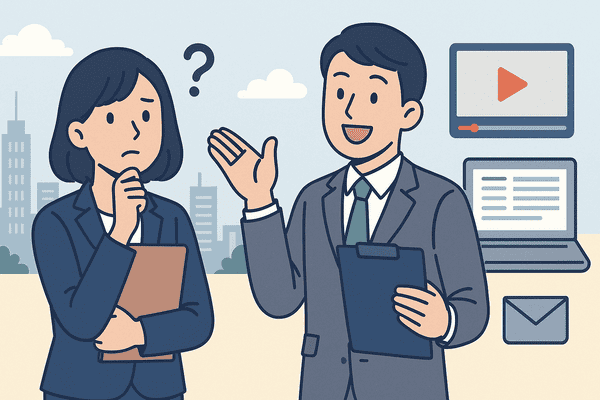
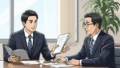
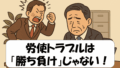
コメント