顧問社労士として、これまで本当にいろんな労使トラブルに向き合ってきました。突然「今すぐ来てください!」と電話がかかってきたこともあれば、事務所で何時間も話し続けてヘトヘトになった日もあります。
「トラブルの解決」と聞くと、多くの人はまず弁護士を思い浮かべると思います。もちろん、法的な解決は弁護士さんの専門領域です。でも、社労士には社労士なりのアプローチがあります。もっと柔らかく、会社と従業員の両方が前を向けるような“着地点”を探していくのが私たちの強みなんです。
この記事では、私が普段の現場で大事にしている考え方や、対応するときに意識しているポイントを、実際のエピソードも交えながらお話ししていきます。ちょっとリアルな現場の空気感も感じてもらえるかもしれません。
なお、この記事は労務管理の一般的な傾向をまとめたもので、特定の個人や企業を指すものではありません。状況によって必要な対応は変わるので、個別のケースでは社労士など専門家に相談することをおすすめします。
労使トラブルはなぜ起こるのか?
今日のテーマは「人を幸せにできる社労士になろう」ということで、具体的には、労使トラブルに関することです。
まず最初にお伝えしておきたいのは、ここでお話しする内容はあくまでも私自身の価値観に基づいたものだということです。特定の誰かを批判したり、考え方を矯正したりする意図は一切ありません。その点をご理解いただければと思います。
顧問社労士として業務をしていると、社長から労使トラブルに関する相談を受ける機会が非常に多いです。正直、「こんなに多いのか」と驚くほどです。
なぜこれほどまでにトラブルが起こるのか。それは、会社と従業員という関係が、本質的に“利害が対立する存在”だからです。
会社と従業員では、立場や優先する価値観が異なるため、どうしても意見のズレが生まれやすい構造になっています。たとえば、会社は経営の安定を重視し、従業員は生活の安心を求める、このズレがトラブルの火種になることもあります。
こうしてみると、両者の利害は一致していないとも言えますよね。もちろん、お互い大人ですから、日常的にはうまく折り合いをつけてやっていけるものです。しかし、ちょっとした誤解や行き違いがきっかけで、その関係が一気に崩れ、大きなトラブルへと発展してしまうこともあります。
ある意味、この構造的な対立は避けられないものかもしれません。
社労士に寄せられるトラブル相談
トラブルの話になると、「弁護士さんに相談するもの」とイメージする人が多いですよね。実際、弁護士の方々もそういう役割を意識して活動していると思います。
一方で社労士は、その“手前の段階”で動くことが多い仕事です。職場の状況を整理したり、会社と従業員それぞれの思いをすり合わせたりして、両者が前向きに話し合えるように環境を整える、そんな立ち位置が社労士なんです。
中小企業の場合、顧問弁護士を置いていないところも珍しくありません。そのため、法的な手続きに進む前の段階で、「まずは事情を聞いてほしい」「感情的にならず整理したい」と、社労士に相談が来ることもよくあります。
もちろん社労士には、法律上、代理や交渉をする権限はありません。でも、事実を丁寧に整理して、スムーズで前向きな話し合いにつなげていくことはできます。現場の空気を整えるのが、私たちの大事な役割だと思っています。
相談内容は本当にいろいろですが、よくあるのはこんなケースです。
- 勤務態度の問題
例:勤務態度に課題がある従業員に指導を行った際、双方の認識にズレがあり、話し合いが難航してしまうケースは少なくありません。 - 未払い残業代
例:退職した従業員から労働基準監督署へ相談があり、その調査の過程で未払い残業代が明らかになるケースもあります。
ここで、「顧問社労士がついているのに未払い残業代が出るなんてどういうこと?」と思われるかもしれません。ですが、現実には理想とギャップがあります。
顧問社労士だからといって、企業が自社の情報を100%開示してくれるわけではありません。もちろん「何でも話してください、開示してください」とお願いはしますが、社長によっては情報を隠したがる方もいます。
社労士は役人ではないため、「全ての情報を開示せよ」と命令する権限はありません。あくまで民間人としての立場なので、初めて知る事実がトラブル発覚時に出てくることもあるのです。望ましいことではありませんが、現実にはこうしたケースが起こり得ます。
労使トラブルが発生すると、当事者同士(つまり社長と従業員)は感情的に対立してしまい、話し合いが進まなくなることが少なくありません。そんなとき、社労士が第三者的な立場で間に入り、状況を整理し、双方が冷静に話せる環境をつくる。これが、現場でよくあるパターンなのです。
労使トラブル解決で気をつけるべきこと
社労士として現場に立つと、頭では分かっていても心が揺れる瞬間があります。ここでは、私が特に大事にしている4つの視点をお話しします。
冷静になること
トラブルが起きて社長から電話がかかってくると、冒頭から声が荒くなっていることがあります。「もう辞めさせたい。どうにかならないか」その気持ちは分かります。人間ですから、感情が先に立つのは当然です。
でも、そこで社長の熱に引きずられてはいけません。日本では「解雇権の濫用」が厳しく制限されていて、感情的な判断で動くと、後々トラブルが長引いたり、裁判に発展するおそれがあります。
そうなると、会社としても大きな負担を抱えることになりかねません。だからこそ、まずは冷静に状況を整理し、慎重に対応することが大切です。
だからこそ、社長が熱くなっているときほど、私は一歩引いて状況を冷静に見ます。まず状況の全体像を落ち着いて把握することが大切です。
事実関係をしっかり見極めること
二つ目。判断の前提となるのは、正確な事実関係です。でも社労士は現場に常駐しているわけではありません。見ていないことを見たように判断するのは危険です。
そのため、会社側(社長や管理職)からだけでなく、当事者本人からも必ず話を聞く必要があります。片方の話だけで結論を出すのは、一番怖いパターン。必ずバランスが崩れます。
複数の関係者から話を聞き、情報を整理・精査して初めて、正しい状況把握が可能になります。以前、パワハラの事案で管理職の話だけを鵜呑みにしそうになったことがありました。
「Hさんは注意してもすぐミスをするので、必要な指導をしているだけです。本人が“パワハラ”と言うのは心外です。」管理職の話はこうだったのですが、Hさん本人に話を聞くと、状況はまったく違いました。
皆の前で強い口調で叱責されることが続き、大きな精神的負担になっていたそうです。同僚からも「確かに言い方はきつすぎる」という証言がありました。
明らかに業務指導の範囲を超えた言動です。本人の声を聞いた瞬間、状況の捉え方を改めなければならないと強く感じました。
必要以上に怖がらないこと
ときには、相手側が弁護士や合同労組の担当者を同席させることもあります。でも、だからって社労士が必要以上に怖がる必要はありません。
ただ、法律的なやり取りとか、主張のぶつけ合いみたいなところは完全に弁護士さんの仕事です。そこは社労士が入っちゃいけないライン。
私たち社労士がやるのは、会社の状況を整理したり、事実をちゃんと確認したり、話し合いがギスギスしないように場を整えたりすることなんです。いわば空気を整える係ですね。
たとえその場で弁護士を呼べない状況でも、社労士なら会社の実務や労務の視点からアドバイスできますし、必要になったら弁護士さんにつないで一緒に動くこともできます。
この「助言・整理・準備」という役割をちゃんと守って関わることで、無理なく健全な形で職場トラブルの解決を支えていける、私はそんなふうに思っています。
双方が納得できる着地点を目指すこと
最後に、これが一番大事だと思っています。社労士は弁護士ではありません。弁護士は依頼人の代理人として勝ち負けを意識し、法廷での決着を目指しますが、社労士はその立場には立てません。
むしろ社労士だからこそ、勝敗ではなく「双方が納得できる着地点」を探ることができます。会社と従業員、両者が少しでも幸せになれる方向を模索する、これが社労士として関わる中で、特に力を発揮しやすいアプローチだと感じています。
具体的には、お互いの言い分をじっくり聞き、感情を落ち着かせた上で、フィフティー・フィフティーの合意点を探していきます。
守秘義務のため詳細はお話しできませんが、あるトラブルで従業員の女性と直接向き合ったとき、彼女が最後にこう言いました。
「私が権利を主張しすぎていることは分かっていました。私はただ、人として扱ってほしかっただけなんです。こうやって向き合ってくれて、本当に嬉しかったです。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。」
この時の笑顔は、報酬以上の価値がありました。やっぱり、人は心で動くんだと実感しました。
まとめ
この記事では、私が考える社労士のあり方について話しました。弁護士さんとは違うアプローチで、トラブル解決をサポートする。そして、最終的には当事者の方が笑って帰って行かれる姿を見ることができる。
それが、この仕事の醍醐味なんじゃないかなって改めて感じました。今後も、社労士として働く上で大切なことを伝えていけたらと思っています。
【執筆者】イタル(社会保険労務士)
社労士開業歴14年目。地域の中小企業の手続き業務、労務管理、相談業務に多数携わる。本ブログでは、実務経験に基づいた一般的な労務知識をわかりやすく解説しています。


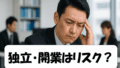
コメント