顧問先から「この人に任せたい」と思ってもらえる社労士になるためには、ある視点の転換が欠かせません。それが「経営者目線」です。
このブログでは、特に企業の顧問として活躍していきたいと考えている社労士の方に向けて、経営者の立場に立つとはどういうことか、どのようにその視点を身につけていくのかを、具体的な事例も交えながら分かりやすくお伝えしていきます。
会社員時代に身についてしまった“労働者としての考え方”をどこでどう切り替えるか。このポイントを押さえることで、顧問先からの信頼を得ることに繋がっていくと思います
社労士の仕事と経営者目線
企業の顧問社労士として活躍していきたいのであれば、「経営者目線」への転換は大切な要素の一つです。この記事では、まさにその大切な“視点の切り替え”についてお話ししていきます。
まず知っておいていただきたいのは、「経営者目線に切り替える」ということは、言い換えれば、他の“目線”(とくに労働者としての視点)のままではうまくいかない事が多いということです。実際、開業したばかりの社労士が会社員時代の感覚のままで顧問契約を目指しても、なかなか成果が出ないケースが多いのです。
会社員から独立して社労士になった方は多くいらっしゃいますが、そのままの価値観や考え方では通用しにくいのが現実です。ある意味、「コペルニクス的転回」とも言えるような、大きな発想の転換が求められるのです。
人間の習性と気づきの重要性
ここで一度、人間の「習性」について触れておきたいと思います。実は、人って誰かに指摘されるまで気づかないことが案外多いんです。
たとえば「コロンブスの卵」の話にあるように、いざ言われてみると「確かにそうだ」と思うことも、言われる前は全く意識していなかったりします。今日お伝えする“経営者目線への切り替え”も、まさにその類いです。
さらにもう一つ大事なのは、「分かったつもり」になっても、実際に自分の考え方として“定着”させるには時間がかかる、ということ。
頭では理解していても、いざ実務の場面で無意識に反応してしまうのは、やはり昔の労働者目線だったりします。だからこそ、まずはそのことに気づくこと。そして、時間をかけて意識的に“慣れていく”ことがとても大切なんです。
社労士の仕事全体像と企業顧問
社労士の仕事といっても、そのフィールドは実に幅広く、関わる相手によっておおまかに3つの方向に分かれます。
ひとつは、個人の方を対象とした仕事。たとえば年金の相談対応などがこれにあたります。
ふたつ目は、労働者の立場に寄り添う支援。労働条件に関する相談や、権利を守るためのアドバイスなどです。
そして3つ目が、今回のテーマでもある「企業の顧問」としてのサポート。
企業顧問と聞くと、「顧問弁護士」や「顧問税理士」のような存在をイメージされる方も多いかもしれません。社労士もそれと同じように、企業の外部パートナーとして、労務や人事の面で経営者を支える役割を担います。
たとえば、従業員とのコミュニケーションに悩む社長に対してアドバイスをしたり、就業規則の見直しやトラブルの予防策を提案したり。労使の揉めごとが起こりそうな場面では、初動対応を社労士が担うケースもよくあります。
もちろん、労働保険・社会保険の手続き業務は社労士の得意分野ですし、会社の成長を後押しする助成金の申請サポートも大切な仕事のひとつです。
こうした日常業務を通じて、社労士は「経営者の右腕」として、現場に密着した支援をしていくことになります。そしてこのスタンスが、そのまま「経営者目線」へとつながっていくのです。
経営者と労働者の根本的な違い
会社の中で日々やり取りをするのは、大きく分けて「経営者」と「労働者」の2種類の立場の人たちです。もちろん、取引先やお客様も関わってきますが、日常的に社内で向き合うのはこの2者が中心になります。
では、その2者の関係性について、どこまで意識できているでしょうか?
試験勉強でも出てきたように、労働契約があることで、経営者は労働者に指示を出し、労働者はその指示に従って働く。そして、その対価として経営者が賃金を支払うという関係が成立します。これが「指揮命令関係」あるいは「使用従属関係」と呼ばれるものですね。
ここまでは多くの方が知っていることかもしれません。でも実は、この関係性の根底には、もう一つ大事なポイントがあるんです。それは、経営者と労働者は、利益においてしばしば“利害が対立する”という点。
「うちは和気あいあいとしてるから、対立なんて感じないよ」という方もいるかもしれません。ただここで言う“対立”とは、感情的なものではなく、経済的な優先事項の違いを指します。
たとえば、労働者は「残業を減らしたい」「給料を上げてほしい」「もっと休みがほしい」といったことに強く関心を持っています。一方、経営者の頭にあるのは「売上はどうか」「利益は出ているか」「会社の未来はどうなるか」といった経営全体のこと。
同じ社内にいても、見ているもの、気にしていることが根本的に違うわけです。だからこそ、社労士として顧問を務めるなら、この“立場によって見える景色が異なる”という前提をしっかりと理解しておく必要があります。
顧問社労士の役割と経営者目線への転換
企業の顧問社労士に求められるのは、「経営者の立場を理解し、その意図を踏まえて助言できる姿勢」です。ここを誤解している方が意外と多く、「労使の間に立ってバランスを取る存在」だと思っている人もいます。
もちろん、法令遵守は大前提ですし、労働者を不当に扱うことは決してあってはなりません。そのうえで、現実のビジネスでは、社労士は経営者と同じ方向を向きながら課題解決を進める“パートナー的存在”としての役割が求められます。
理想だけで語っても、信頼は得られませんし、顧問契約も続きません。だからこそ現実を見て、社長の立場に立ってものを考え、提案していく姿勢が求められるのです。
ここで一つ強くお伝えしたいのは、「会社員時代の思考をそのまま持ち込んでは通用しない」ということです。
あなたが以前、労働者としての立場で働いていたのであれば、そのときの価値観や物の見方が無意識のうちに染みついているはずです。それを転換していかなければ、企業顧問としては信頼を得にくくなります。
「労働者目線」から「経営者目線」へ。これは単なる立場の違いではなく、大きな思考改革です。
実際、私自身も開業して間もない頃、ある経営者からこんな言葉をかけられたことがあります。「そんな答えなら労働基準監督署でも聞ける。わざわざ社労士に依頼している意味がないじゃないか・・」
その瞬間、ハッとしました。私は“正しい知識”を伝えたつもりだったのですが、社長が本当に求めていたのは「経営を続けるための現実的な選択肢」や「企業の味方としての助言」だったのです。
この経験を通じて、「経営者目線に立つ」という意味を、頭ではなく“感覚”として理解できるようになりました。
普段の何気ない言動にも、この目線の違いは如実に表れます。だからこそ、まずは「意識すること」、そして「習慣として身につけること」が大切なのです。
これを知った今、あなたの中で何かが変わり始めたなら、その一歩こそが“選ばれる社労士”になるための出発点です。
経営者目線での具体的な例
ここからは、「経営者の視点って実際どんな考え方なのか?」をイメージしやすいように、よくある3つのケースを取り上げて考えてみましょう。
① 働き方改革で“休暇を増やす”提案
最近では、誕生日休暇や記念日休暇など、ちょっとユニークな制度を提案する社労士も増えてきました。従業員のモチベーションアップにつながる取り組みとしては魅力的ですよね。
ただ、ここで忘れてはいけないのが、その提案を受け取る経営者側の視点です。「うちの社員はまだ有給すらしっかり消化できていないのに、さらに休暇制度を増やす余裕なんて本当にあるのだろうか?」こうした感覚を持つ社長も少なくありません。
下手をすると、「この人、ウチの事情をちゃんと分かってるのかな?」と思われてしまうこともあります。
② 「残業時間の抑制」よりも「残業代コストの最適化」を考える
残業を減らすことは、働き方改革の中でも大切なテーマです。でも、「残業時間を減らすこと」と「残業代のコストを下げること」は、必ずしも同じ意味ではありません。
現実には、業務量は変わらないのに人件費だけが増えてしまうケースもあります。そんなときに検討できるのが、労働時間の仕組みそのものを見直す方法。たとえば「変形労働時間制」や「裁量労働制」、「定額残業代制度」などです。
経営者にとっては、こうした“費用の見通しが立てやすい制度”は大きな関心事です。だからこそ、制度の仕組みを分かりやすく説明しながら、「御社の場合ならどう導入できるか」を一緒に考えていくことが大切になります。
③ 労働者への“擁護的な言い回し”に注意
気をつけたいのが、良かれと思って発した言葉が、経営者には“労働者寄りすぎる”と映ってしまうケースです。
たとえば、社長から「トラブルを避けるにはどうすればいい?」と聞かれた場面。ここで「従業員が納得できる仕組みを作りましょう」と答えると、一見正論ではあるのですが、「うちの立場も分かってくれているのかな」と不安を持たれることもあります。
そんなときは、「御社の方針を踏まえたうえで、できるだけトラブルを未然に防げるよう一緒に考えていきましょう」といった言い回しに変えると、伝わり方が違ってきます。
これら3つのケースに共通しているのは、こちらの意図がどうであれ、相手の立場によって受け取られ方は変わるということです。
経営者と信頼関係を築いていくためには、日常の会話や提案の中で「同じ方向を見ている」というメッセージが自然と伝わるように意識すること。それが大きなポイントになると思います。
社長に選ばれる社労士になるために
社長が顧問社労士を選ぶとき、最も重視するのは「自分の目線に立って、一緒に会社を良くしてくれる人かどうか」です。
いくら知識や実務経験が豊富でも、経営者の感覚に寄り添えない人であれば、信頼関係は築けません。その意味で、“経営者目線で物事を考えられるか”というのは、顧問契約を勝ち取るか否かを左右する、大きな分かれ道になります。
逆に言えば、たとえ実務経験が浅くても、経営者の立場を理解しようとし、同じ方向を向いて提案や対応ができる社労士であれば、長く信頼される存在になれるのです。
独立したばかりの方にとっては、つい「労働者側の視点」が抜けないこともあると思います。でも、今回お伝えしたように、そこにまず“気づく”こと、そして“慣れていく”努力を続けることが、何よりの差別化要因になります。
社長にとって、数ある社労士の中から「この人に相談したい」と思える存在になるために、まずは今日から少しずつ、「経営者ならどう考えるか?」という問いを、日々の業務に取り入れてみてください。
その積み重ねが、やがてあなたを“選ばれる社労士”へと導いてくれるはずです。
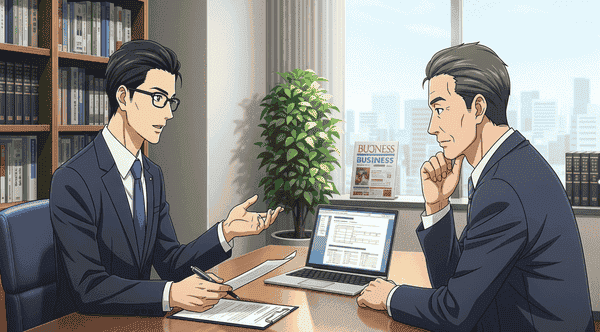
まとめ
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。最後に、今回お伝えしてきたポイントをあらためて整理しておきます。
社労士として長く選ばれ続けるには、知識やスキルに加えて、「どれだけ経営者の立場に寄り添えるか」が大きな鍵になります。
今日の内容が、あなたの思考を少しでも経営者寄りにシフトさせるきっかけになれば嬉しいです。焦らず、ひとつずつ。現場での経験を重ねながら、じっくりと“経営者目線”を育てていきましょう。
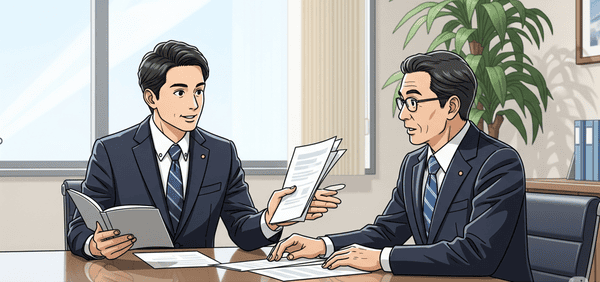


コメント