仕事中に頻繁に居眠りをしてしまう従業員への対応に悩んだことはありませんか?その居眠りを放置してしまうと、労働力の低下や職場の士気の低下にもつながりかねません。
この記事では、開業14年の社労士が、仕事中の居眠りの原因を突き止め、会社として取るべき適切な対応について解説します。居眠りの原因が病気の場合、そうでない場合など、ケース別にどのような対応策があるのか、具体的な方法を知ることができます。
居眠りは労働契約の不完全履行
労働者は労働契約に基づいて、労務提供義務を負っています。居眠りをしているということは、仕事をしていないので、労務提供をしていないという状態にあります。仕事中に頻繁に居眠りをしているということは、これは労務提供が不完全な状態であるということが言えます。
それから職場の風紀秩序を乱すことにもなります。隣の席の人は「あれ、この人また寝てるの?この寝てる間にもお給料出てるの?なんかやってられないわ」と、周りの人間もモチベーションが下がってしまうということもなりかねません。
そこで、会社としては何らかの対応を取る必要があるんですが、一体どのような対応を取ればよいのでしょうか。
居眠りの原因をまず確認する
まず、その居眠りの原因は何かということなんですが、大きく分けて病気が原因の場合と、病気ではない場合の2つに分かれます。
病気が原因の場合
睡眠時無呼吸症候群やナルコレプシーなど、医学的な要因によってどうしても眠ってしまうケースがあります。こうした場合は、本人の努力だけで解決するのは難しいので、医療機関で診察・治療を受けてもらうことが必要です。
実際に顧問先の従業員の中に、仕事中どうしても眠気が強く出てしまう方がいました。本人も“寝てはいけない”と思っていても抑えられない様子で、後日病院を受診したところ睡眠時無呼吸症候群と診断されました。治療を始めてからは見違えるほど改善したのを覚えています。
この病気が原因かどうか、これは我々には判断できませんので、医学的なことはお医者さんにしか判断ができません。当然医療機関に行って診察を受けていただくということになります。
その従業員さんが素直に受診してくれればいいのですが、そうではない場合に会社の方から「あなたは仕事中にこれだけ居眠りをしてしまうということは、病気の可能性も考えられるので、一度お医者さんに行って見てもらってください」ということになります。
それで素直に「はい、わかりました」と言ってくれればいいんですが、中には「いや大丈夫ですよ、そんな病気じゃないですよ、なんでそんなこと言うんですか」と言ったり、あるいは「その病気のことなんか言いたくないですよ、なんでそんな診断書出したりしなきゃいけないんですか」と言われてしまうこともありえますよね。
そこでスムーズに対応できるように、就業規則に「業務上必要がある場合には受診や診断書の提出を求めることがある」というルールを定めておくと安心です。
治療期間中の対応について
そして、治療していただくわけなんですが、通常の業務を続けながら治療できる場合とできない場合があるかと思います。下記のようなパターンが考えられます。
補足しますと、治療に専念していただくとしたら、比較的短い期間であれば、年次有給休暇を取得していただいて、治療していただくことができるかと思います。
年次有給休暇がもうないというような場合には、欠勤していただくと病気欠勤というような扱いになります。(ノーワークノーペイの原則に基づいて、働かなかった部分は賃金は支払われないとその分給与が減額)
年次有給休暇を取得すれば給与は減らない、欠勤すれば給与が減ってしまう、こういった違いがあります。
それから、その治療期間がかなりの期間にわたるというような場合には、会社に休職制度があれば休職していただくというようなことになると思います。
この休職制度の内容は会社によってまちまちですので、まずは就業規則を確認してください。一般的には勤続年数に応じて休職期間というのが定められていて、その休職期間が満了しても復職できない、つまり治癒していない、こういう場合には自然退職になるというような規定になっているのが一般的です。
会社によっては休職制度がない会社もあります。休職制度というのは法的な義務ではないので、必ずしも休職制度を定める必要はないんですね。
それでは休職制度がない場合どうするかと言うと、場合によっては労働契約の解消、「もう正常な労務提供が難しいんじゃないですか」ということで、「じゃあ労働契約解消しませんか」というようなことで退職勧奨、または普通解雇になります。
ただし、この普通解雇、解雇というのはどのような解雇であっても不当解雇だと、言われるリスクというのはありますので、できれば避けたいところですよね。
なるべく労働契約を解消する場合でも、話し合っていただいて、退職勧奨に応じていただいて合意退職、こういったところで落とし所を見つけていただければと思います。
病気ではない場合の対応
次に病気ではないケースですね。居眠りの原因は特に病気ではないというような時に、また2つに分かれると思います。原因が本人が悪い場合と、会社に責任がある場合2つに分かれると思います。
実際に、顧問先の若手社員が「夜はついゲームに夢中になってしまって…」と正直に話してくれたことがありました。そのときは始末書までは求めず、生活習慣の改善を促す形で面談を行ったところ、次第に勤務中に居眠りすることもなくなっていきました。
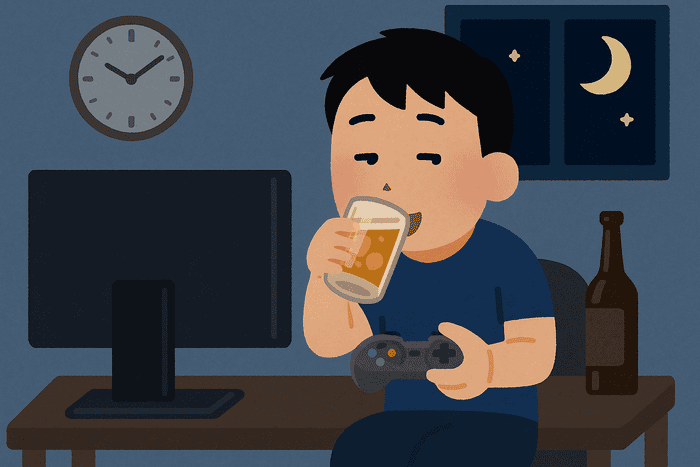
要するに、会社が原因の場合は残業を減らすなど環境改善を、本人が原因の場合は「それをやめてください」と指導することになります。
注意・指導から懲戒処分へ
本人に原因がある場合、「まずは注意して改善を促す」ことが基本です。話し合いや指導で改まればそれで良いのですが、繰り返しても改善されない場合には懲戒処分を検討せざるを得ません。
懲戒処分には次のように段階があります。(下に行くにしたがって重い処分となる)
いきなり重い処分を下すことは認められず、段階的に進める必要があります。特に居眠りを理由にいきなり懲戒解雇をするのはハードルが非常に高く、現実的には難しいのが実情です。
まず始末書を書かせるといった軽い処分から段階的にやっていく必要があります。始末書を何度書かせても改まらなければ、減給処分と重い処分にしていきます。
それでも改まらなければ、やはりちょっと勤務を続けることは難しいんじゃないですかねということで、労働契約を解消する方向、先ほどのように退職勧奨や普通解雇こういったことをやらざるを得ないということになろうかと思います。
重ねてになりますが、この解雇というのはどのような場合でもやっぱりハードル高く、不当解雇だと言われる危険性があります。
ですから、なるべくなら解雇ではなくて退職勧奨、ちょっと難しいんじゃないですかということで、労働契約を解消しませんかということで、合意退職、こういったところが一番いいんじゃないかなと思います。
副業が原因の場合の補足説明
本人に居眠りの原因がある場合の理由の一つとして、「無許可で夜に副業」と書きましたけど、これには次のような背景があります。
副業については昔は「原則禁止」とする会社が多かったのですが、最近は「原則認めるが届け出は必要」という方向に変わってきています。最近では厚生労働省のモデル就業規則でも、原則として認めるような規定になっているんですね。
ただし、すべてが自由というわけではありません。
上記の場合には禁止とする規定を置く企業が多いです。例えば競業他社での業務であるとか、その仕事をすることで会社の信用が著しく害される場合、こういった時は禁止されることが多いです。
また、深夜に肉体労働の副業をして、翌日眠くて仕事にならないというのは典型的にアウトです。
実際に、ある顧問先で深夜にアルバイトをしていた従業員がいました。昼間の勤務中に強い眠気で集中できず、業務に支障が出ていたのです。会社に内緒で行っていたのですが、たまたま社員がその店を訪れたことで発覚しました。
就業規則で副業は「届け出制」としていたため、事情を確認したうえで会社から正式に副業の中止を指導しました。その後は勤務態度も改善し、同僚からの不満もなくなったのを覚えています。
無断でこうした副業をしているなら、就業規則に基づいた対応が必要です。
まとめ
労務提供が不完全なだけではなく、職場全体の雰囲気も悪くなりかねないから、会社として何らかの対応を取ることはとても大切です。
また、スムーズな対応のためには「受診命令」「副業の届出」「懲戒処分の手順」などを就業規則に明確に定めておくことも重要です。
この記事が今後の労務管理や就業規則の見直しの参考になれば嬉しいです。


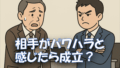
コメント