忙しいサラリーマンの方が、資格取得を目指そうと思うことは少なくありません。私も日々の仕事に追われながら、家庭では2人の子育て中の共働き。住宅ローンも抱えていました。決して余裕のある生活ではありませんでしたが、何とか平穏な日々を送っていました。
それでも心のどこかで「このままでいいのだろうか」という思いを抱えていたのです。
当時の私は、大学では経済学部を卒業し、IT企業でハードウェアのカスタマーエンジニアとして働いていました。簡単に言えば「コンピューターの修理屋」です。一般的なパソコンではなく、企業の基幹システムを支えるサーバーなどを扱う仕事でした。
ハードウェアの故障があれば現場に駆けつけて修理をするという働き方だったため、時間は不規則で、残業や休日出勤も日常茶飯事でした。
このような環境の中で、なぜ私は「社労士を目指そう」と思ったのか。そして、仕事と家庭を両立しながら、どのように資格取得に挑戦していったのか。
この記事では、社労士という資格に挑戦することになった理由と、その背景を、私自身の体験をもとにお話しします。今、仕事が忙しくて資格勉強を迷っている方や、「自分にもできるだろうか」と不安を感じている方にとって、何か一つでも参考になれば幸いです。
社労士を目指したきっかけは“人の働き方”への違和感だった
カスタマーエンジニアであった私が担当していた業務は、企業のサーバーなどを修理する業務で、昼夜問わず障害対応が求められる過酷な現場でした。特に大変だったのが、月に数回回ってくる「夜間の障害対応当番」です。
当番の日は、自宅でもコールセンターからの呼び出しに備え、枕元に携帯電話を置いて眠り、携帯が鳴ればどんな時間でも必ず飛び起きて電話に出なければなりません。眠りも浅くなりがちです。「どうか今日は携帯が鳴りませんように」と祈るような気持ちで布団に入り、朝まで呼び出しがないだけでホッとする、そんな日々が続いていました。
もちろん、呼び出しが実際にある日もあります。夜中に障害の連絡が入れば、すぐに近所のタクシー会社の営業所に電話し、タクシーに乗ってそのまま現場へ直行します。深夜2時に呼び出しがあり、朝8時まで復旧作業ということもありましたし、また、何度も同じ運転手さんの車に乗ることがあり、「いつも大変ですね」と声をかけられたこともありました。
現場では、障害が復旧して「助かりました、本当にありがとうございます」と感謝されることもありました。一方で、障害が長引いて業務に大きな支障が出てしまう場合には、お客様から厳しい言葉を投げかけられることも少なくありませんでした。
さらにもう一つの理由としてあったのが、「このままこの仕事を続けていく自信が持てなくなってきた」という気持ちです。私は経済学部の出身で、もともと文系です。エンジニアとしてある程度の経験は積んできましたが、周りには理系出身の優秀な同僚も多く、次第に「この分野でトップに立つのは難しいな」と感じるようになっていきました。
そして自分のキャリアについて真剣に考えるようになりました。そんな折に書店の資格コーナーでふと目にしたのが「社会保険労務士(社労士)」という資格でした。
妻が看護師をしていた関係で、資格を生かした仕事には以前から興味がありました。妻のことを、ちょっぴりうらやましくも思っていたのです。
社労士に惹かれたのは、人事労務や働き方に関わる国家資格であり、まさに自分が違和感を抱いていた「働き方」そのものに向き合える仕事だったからです。
さらに、社労士は決して簡単な資格ではありませんが、司法試験のように現実離れしているほど難しいわけでもない、という点もポイントでした。実際に調べてみると、時間をかけて努力をすれば合格を目指せるレベルであることもわかり、「これなら現実的に挑戦できるかもしれない」という気持ちが芽生えたのです。
資格も法律もゼロからのスタート
社会保険労務士を目指そうと思ったとき、私は法律の知識はまったくのゼロでした。大学は経済学部で、仕事はIT系のハードウェアエンジニア。法律とは無縁の世界です。もちろん社労士の「しゃ」の字も知らない状態でした。
ただ、だからといって躊躇しようとは思いませんでした。むしろ、今の自分を少しでも変えたい、現状から抜け出したいという気持ちの方が強かったのです。本音を言えば、「このままエンジニアを続けても、上には行けないだろうな」とも思っていました。
現場の最前線で障害対応をし、休日も夜中も働いているのに、ふと社内のメールを見ると、管理部門の人たちは定時で帰っている。「なんだか、ずるいな」「楽そうでいいな」当時はそんな風に思っていました。
もちろん、今にして思えば、それぞれの部門に違った大変さがあることもよく分かります。実際に私が後に人事に異動してからは、想像以上に神経を使う仕事が待っていました。
でも、当時の私にとっては、管理部門=ホワイトな働き方、現場=過酷で評価されにくいという印象があったのです。
そんな中で、もし資格を取って人事や労務の分野で働ければ、「もっと人間らしい働き方ができるんじゃないか」「現場を支える立場に回ることができるかもしれない」そう思うようになりました。
そしてもう一つ、資格を取れば転職の道も開けるかもしれないという打算的な気持ちや、独立開業できるかもしれないという気持ちも、正直ありました。
社労士の資格は、働き方や労働環境に直接関わる資格です。自分が違和感を覚えてきた「働き方」そのものに関われること、そして、難しすぎないけれど本気で勉強すれば手が届くかもしれないという「ちょうどいい難易度」も魅力でした。
そんな風にして、まったくの初心者だった私が、ゼロから社労士を目指す決意をしたのです。
妻の反対と、納得してもらうまで
当時の私は、仕事だけでなく家庭でもなかなか大変な状況にいました。子どもは2人。子どもはまだ保育園に通っていて、しかも共働き。妻は看護師で、こちらも激務。私もITエンジニアとして残業や休日出勤が多く、毎日がギリギリの綱渡り生活でした。
保育園の送り迎えは分担していて、私は朝の送りを担当。夜は残業で帰りの時間が読めないため、迎えは妻が担当する形でした。どちらが欠けても回らない、そんな毎日です。
当初妻の理解は得られなかった。
そんな中、「社労士の資格を目指したい」と妻に話したとき、彼女はとても驚いてこう言いました。
「こんな状況で勉強するなんて難しいんじゃないの?」「家族に迷惑かけずにできるの?」
その反応は、ある意味当然だったかもしれません。私の中では少しずつ悩み抜いて出した決意でしたが、彼女にとっては“青天の霹靂”だったのです。
でも、私はどうしてもこの資格に挑戦したかった。自分の働き方を見直すためにも、今の生活を変えるためにも、子どもたちに、何かを一生懸命やりきる姿を見せたいと思ったからです。
根気よく妻を説得
だからこそ、真正面から妻と話をしました。なかなか話を聞いてもらえず、感情的になりかけた場面もありました。そういう時には、数日おいて、その間、洗濯や掃除、休日は朝昼晩の三食とも私が料理を作るなど家事を頑張り、妻が機嫌のいい時を見計らって再度話をしました。
なぜ目指したいのか、通勤時間や隙間時間を勉強に充てて、できるだけ工夫して勉強することなどを、一つひとつ丁寧に伝えました。短期的には勉強のため妻に負担をかけることがあっても、長い目で見れば合格後、結果的にもっと家事も行えるようになる、ということを強調して、根気よく妻を説得したのです。
当時、その話をした時期は1月で、8月に行われる次の社労士試験までの残り期間はたった7か月でした。社労士試験合格に必要な勉強時間は資格予備校の資料によると、一般的におよそ1,000時間程度といわれています。これは1日約3時間毎日勉強して1年かかる時間です。
すぐ本格的に始めても、私の1日にとれる勉強時間を考えたら、どう工夫しても7か月後の合格は現実的ではありませんでした。そこで私は1年半後の8月に合格する計画を立ててこう妻に伝えました。
「今から1年半、本気で取り組ませてほしい。それでも合格できなかったら、あきらめる。約束する。」
家事をする時間や子どもと遊ぶ時間が少なくなるなどの影響を考えると、合格までずるずると何年もチャレンジするわけにはいきませんでした。その“覚悟”と最終期限を決めて退路を断ったのが功を奏したのか、最終的に妻は、「そこまで言うなら、やってみなよ」と納得してくれました。
合格後のメリットを説明したことにより、家族の理解が得られたことが、最初の大きな一歩になったのです。
※当時、共働き・子育て・残業ありの中で「1年半の合格計画」をどう回したかは、「忙しい社会人でも続けられる!1年半で社労士試験に合格した勉強時間の作り方」で具体的にまとめています。
まとめ
学生生活や就職してからの人生を思い返せば、これまで私は何かに全力で打ち込んだことがありませんでした。
高校受験も、大学受験も「なんとなく」で、特にやりたいことがあったわけでもありません。大学も「つぶしがききそう」という理由で経済学部を選び、就職も流れに身をまかせて決めたようなものでした。
そんな“なんとなく”の人生を送ってきた私が、なぜか社労士という資格を目指すと決めたときだけは、違っていました。「これに、かけてみたい・・・」理由をうまく言葉にできなかったけれど、このままでは終わりたくないという思いと、“自分で決めて、自分で勝ち取りたい”という強い気持ちが、心の奥から湧いてきたのです。
もちろん、家族の協力なくしては始めることすらできなかった挑戦です。妻との話し合いを経て、1年半という期限付きでチャンスをもらい、私は人生で初めて「本気で挑む」というステージに立つことになったのです。
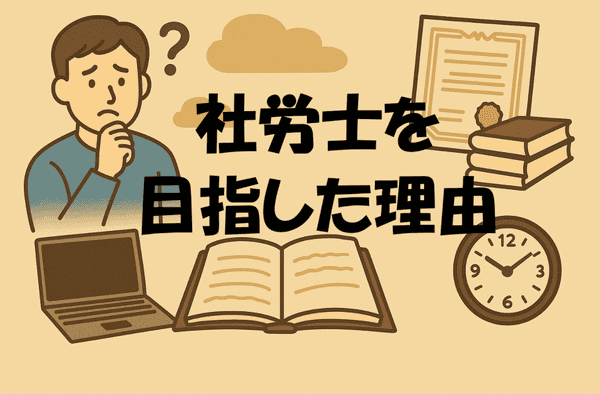
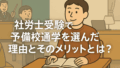
コメント