社労士として独立開業したとき、多くの人が最初に直面するのが「顧客ゼロからどうやって契約を取るか」という課題です。私自身も、開業当初は全く顧客がいない状態からのスタートでした。
この記事では、開業社労士が顧客を獲得するために実際にどのような営業を行ったのか、そしてその過程で直面した現実や乗り越えるための工夫についてお伝えします。営業の基本的な考え方から具体的な行動まで、これから独立を目指す方の参考になれば幸いです。
顧客獲得の現実と心構え
開業社労士にとって絶対に避けては通れないのが「顧客のつかみ方」、つまり営業方法です。営業ができなければ、どんなに知識やスキルがあっても、仕事として成り立ちません。それくらい大事なテーマです。
さて、どうやって営業して顧客をつかむのか?実は、成功されている先輩社労士の方々も、ある程度決まった方法を駆使して顧客を獲得しています。その方法はいくつかあり、ひとつに絞るのではなく、いくつかを組み合わせて実践している方が多いです。
わたしも今回紹介する方法のうち、いくつかを組み合わせて営業しています。
今回は、その代表的な営業方法をピックアップしてご紹介します。どれもすぐにでも取り入れられるものばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。
具体的に、開業社労士が顧客をつかむための営業方法としてよく挙げられるのは、以下の7つです。
どれも一度は耳にしたことがある手法だと思います。資格予備校や通信教育の宣伝では、資格を取ればすぐに稼げるかのような夢のある話が多いのも事実です。
しかし、現実にはいいことばかりではありません。営業は思った以上に地道で厳しい場面が多く、最初はなかなか結果が出ず心が折れそうになる方も少なくありません。
しかし、どの方法も「絶対ダメ」というわけではないのです。実際に、これらの方法のどれかで成功されている先輩社労士が必ずいます。つまり、全体としては厳しい現実があるものの、それぞれの方法で成果を出している人もいる。これが営業のリアルです。
代表的な営業方法とその実態
これから一つずつ営業方法について詳しくご説明していきます。少々ネガティブな話も出てくると思いますが、現実を知った上で取り組むことで、失敗を減らし、結果に近づくことができるはずです。
ぜひ「現実を踏まえた営業方法」として参考にしていただければと思います!
飛び込み訪問:3日で挫折した理由と得た教訓
まず最初に取り上げたい営業方法は「飛び込み訪問」です。「営業といえばこれ」と思う方も多いのではないでしょうか。ひと昔前までは、新卒の新入社員研修でもよく取り入れられていましたよね。それだけ代表的で、王道とも言える営業手法です。
ただ、言うまでもなく簡単ではありません。営業に慣れていない人にとっては、かなり精神的にきつい方法です。なぜなら、断られるのが当たり前で、時には冷たくあしらわれたり、心ない対応をされたりします。
私自身も開業当初、何もお客さんがいない状態から飛び込み訪問をやりましたが、すぐに心が折れてしまいました。非常に冷たく対応されると耳にすることもあります。現実として対応した方がかなりお怒りで、「今はとても忙しい」と強い口調で断られたことがありました。
「これしかない!」と必死に取り組んでいるときに冷たくされると、かなりダメージを受けます。だから、心が弱い人や営業に不慣れな人には正直おすすめできません。
一方で、営業経験が豊富で、断られても気にせず切り替えられる人にとっては大きな武器になります。特に中小企業への訪問では、タイミングが合えば社長と直接話ができることもあります。社長と会えた時点で大きなチャンスを掴める可能性があるのが、飛び込み訪問の最大の魅力です。
「絶対にこれで結果を出したい」という強い気持ちと、失敗してもめげない精神力がある方には、挑戦する価値がある営業方法です。
ただし、都市部などは企業が比較的集中していますが、地方や住宅地などは企業が点在していて距離が離れていますので、移動に時間がかかり、件数が稼げないので、あまりお勧めできません。
わたしも飛び込み営業を3日間行ってみました。私の場合、業種などは絞らず、事務所がある市内の会社にローラー作戦で訪問しようとしましたが、1日に20件ほどしか訪問できず、受付で断られるだけで全く話も聞いてもらえなかったので、早々にあきらめ、他の営業方法に変更しました。
さらに厳しかったのは、体力的・精神的な負担です。訪問先は地図を見ながら一軒一軒回る必要があり、距離もまちまちで、移動だけでもかなりの労力がかかりました。また、会社の前まで来ても「迷惑がられないか」といった不安に襲われ、インターホンを押すことすら躊躇してしまうことが何度もありました。ドアを開ける勇気が出ず、結局そのまま立ち去ったこともあります。
この経験から、「飛び込み営業は気合いと根性だけでは続けられない」ということを痛感しました。行動力ももちろん必要ですが、それ以上に、心を折られないメンタルと、合理的に動ける計画性が求められる営業手法だと思います。
テレアポ(電話営業):100件に1件の出会いが突破口に
飛び込み訪問の次に私が取り組んだのが「テレアポ」、つまり電話営業です。テレアポも「断られて当たり前」の世界ではありますが、意外にもこちらは継続することができました。
飛び込み営業は、会社の前まで行ってもインターホンを押す勇気が出なかったり、ドアを開けられず立ち去ってしまうこともありました。断られるのが怖いというより、「迷惑じゃないか」「怒られたらどうしよう」といった不安が強く、精神的にかなり消耗してしまったのです。
その点、テレアポは相手の顔が見えないぶん、良い意味で感情移入せずに対応できました。「これは仕事だ」と割り切って、スクリプト通りに淡々と電話することができたのが大きかったです。
テレアポのもう一つの良さは、テンポよく数をこなせることです。飛び込み営業では1日20件まわるのがやっとで、1回断られるごとに移動の間モチベーションが下がっていきました。
しかし、テレアポなら断られてもすぐ次の番号にかければいいだけ。1件1件に深く落ち込まず、スピード感を保てるのが続けられた理由です。
私は、NTTの職業別電話帳(無料配布)を活用し、片っ端から電話をかけました。「○○市の地域密着で活動している社労士です。本日は業務案内でお電話しました。」とストレートに伝え、あとは誠実に対応するのみです。
当然、事務員の方でストップされることが多く、社長と話せるのはごく一部。さらに社長に繋がっても、アポイントに至るのはさらに少数です。
私の実体験と当時の記録をもとにすると、架電100件あたりでおおよそ1件のアポイント、訪問10件あたりで1件ほどの成約につながる傾向がありました。つまり、私のケースでは「約1,000件の架電で1社と契約できた」計算になります。
もちろん、業種や地域、時期、トーク内容によって結果は大きく変わりますので、あくまで一つの参考値としてご覧ください。
中には、まさに今「社労士を入れようと思っていた」「就業規則を見直したいと思っていた」という会社に当たることもあります。そんな出会いがあるからこそ、コツコツ続けていく価値があるのです。
テレアポは冷たくされたり、電話をガチャ切りされたりと、決して楽な道ではありません。ですが、私の場合は飛び込みよりも精神的なダメージが少なく、数をこなせる営業方法でした。
私と同じように、営業経験ゼロからテレアポで顧客を獲得している社労士の方もたくさんいます。大事なのは、続けること。数をこなすこと。折れないメンタルを持つこと。
「どうしても成果を出したい」そんな思いがあるなら、テレアポは十分にチャンスのある営業方法です。
DM(ダイレクトメール)・FAXDM:千通送っても反応ゼロ?コスパと工数の現実
飛び込み訪問やテレアポがあまりに辛いと感じた方が、次に試すことが多いのがDM(ダイレクトメール)送付です。実は私自身もそうで、飛び込み営業をやめた後にDMにチャレンジしました。
DMのやり方は単純です。まず、送る先をネットで調べたリスト業者等から有料で入手し、自分で原稿を作って封筒に入れ、郵送します。ここでよく言われるのが「センミツの法則」(1,000通送って3件反応”の意)です。ご存知ですか?
士業の世界では、DMを1,000通送っても反応があるのはせいぜい数件。契約どころか、電話やメールで問い合わせがあるだけで「上出来」とされる厳しい現実があります。実際、1,000通送って反応が3件あれば「成功」とされるほど、反応率は低いのです。
個人で1,000通送るのはほぼ不可能です。リストを入手して、原稿を作成し、宛名シールを作り、封筒を用意して印刷し、封入して、DMシールを貼り、切手を貼る…。千通ともなると膨大な作業になります。
切手を何百枚も貼るなんて、現実的ではありませんよね。なので大量に送る場合は業者に依頼することになりますが、当然お金がかかります。
私は当時、業者には頼まず個人でやりましたが、封入作業などが大変で、200通送るのが限界でした。千通の5分の1にあたる200通だと、計算上は反応ゼロが当たり前。実際、何の反応もないことがほとんどでした。
一度に数百通単位で送らないと効果が見えにくく、個人で続けるのは金銭的にも体力的にも厳しいのが正直なところです。
またDMに似た方法でFAXDMもあります。こちらは原稿を郵送ではなくFAXで送るのです。これも代行業者があります。私はリスト選定も含めて代行してくれる業者にお願いしたので、DMよりは楽でした。
私の結果は、事務所案内を内容にしたDMでは、400通ほど送って反応はゼロでした。助成金や法改正の案内をFAXDMしたときは、1,200件ほど送付して、反応は2件でしたが、依頼には結び付きませんでした。
ただ、やり方と原稿の内容次第では興味を持ってもらえる可能性もあります。資金的に余裕があるなら、業者を活用して大量に送付することも検討してみると良いかもしれません。
※DMやFAXDMは受け取る側にとって負担感があり、「迷惑だ」と感じられることも少なくありません。実際に行う場合は、コストや労力に見合うかどうかを十分に検討し、慎重に取り組むことをおすすめします。
交流会(異業種交流会・士業交流会):名刺交換で終わらせない“関係づくり”のコツ
開業すると、異業種交流会や士業交流会の案内を目にする機会が一気に増えます。異業種交流会は、さまざまな業種の経営者が集まる場で、士業交流会は弁護士、公認会計士、司法書士、社労士、行政書士など「士」のつく専門家だけが集まる交流会です。
どちらも「ここで人脈を作ればお客さんが増えるかも!」と期待して、目を輝かせて参加する方も多いでしょう。
特に異業種交流会では、社長クラスの人が多く集まります。士業にとって社長は潜在的な大きなお客様ですし、士業交流会であれば税理士さんをはじめとした他士業の方とつながり、仕事を紹介してもらえる可能性もあります。まさにチャンスの宝庫に思えますよね。
費用も2,000円から数千円程度で参加できるものが多いので、私も開業当初にたくさん参加しました。しかし残念ながら、私の場合は異業種交流会・士業交流会でお客さんになってくれた方は一人もいませんでした。
その理由は明確で、こういった会に来ているのは、すでにビジネスがうまく回っていて余裕がある社長や士業ではなく、起業・開業したばかりで自分の商品やサービスを売り込みたい人ばかりだからです。つまり、私と同じく「お客さんを探しに来ている人」が集まっている場所なんですね。
実際に参加していると、名刺を交換しても相手は私の名刺をろくに見ずにすぐにしまい、そこから自分の商品の宣伝を延々と始める人が少なくありません。こちらの話にはほとんど耳を貸さず、自分の営業トークばかり。
そういう方に「この人から何か買おう」と思うでしょうか?人間は自分を尊重してくれない相手には心を開きませんよね。自分の話ばかりして相手への興味を示さない人が多いのが、異業種交流会・士業交流会の現実だと感じました。
もちろん、交流会に行くこと自体を否定するわけではありません。ただ「交流会に行けばお客さんができる」という甘い期待は持たず、あくまでも経験や情報交換の場として割り切った方が気持ちが楽だと思います。
異業種交流会や士業交流会は、1〜2時間程度で終わることが多く、たくさんの人と名刺交換できるのが魅力に思えるかもしれませんが、初回の出会いだけでお客さんになるケースはまずありません。一度会っただけではお互いのことを深く知る前に終わってしまい、そのまま連絡が途絶えてしまうのが現実です。
では、異業種交流会を活用して見込み客を見つけるにはどうすればいいのか。おすすめなのは、交流会で知り合った人と数人で、お客様を紹介しあうようなグループを作ったり、継続的に同じ交流会に参加したりして、定期的に顔を合わせることです。
定期的に集まって情報交換をしたり、お互いのビジネスを深く知り合ったりする機会を持つことで、徐々に信頼関係を築けます。
実際に、こういった形で異業種交流会で知り合ったメンバーと定期的に集まり、その関係から仕事につなげている方もいました。単発の交流会で一度だけ会うよりも、何度も会う中で人となりを知ってもらい、「この人なら安心して仕事を任せられる」と思ってもらえることが大切です。
つまり、異業種交流会や士業交流会は「単発参加で名刺を配るだけ」で終わらせず、その出会いを次につなげる工夫をすることで、本当のチャンスが生まれます。
SNS:時間をかけて育てていくことが必要?
次はSNSについてです。開業にあたって、「まずはSNSアカウントを作ろう」と考える方も多いと思います。私も例に漏れず、Facebookのビジネス用ページを立ち上げました。ただ正直に言うと、それ以上の活用はほとんどできていません。
というのも、当時の私は「まず目の前の顧客をどう増やすか」に集中しており、飛び込み営業やテレアポといった“地道だけど即行動できる営業”に力を入れていました。SNSのように時間をかけて育てていくメディアよりも、直接動ける手段を優先していたのです。
それでも、やっていないからこそ見えてきたこともあります。SNSは、たしかにうまく使えば強力な集客手段になります。特に開業直後の知名度ゼロの段階では、「知ってもらう場」として一定の意味があるとも感じます。
ただ一方で、SNSは多くの人にとってプライベートな空間。そこに唐突にビジネス色を出しすぎると、かえって敬遠される可能性もある。仮にやるのであれば、「売り込み」ではなく「人柄や専門性が自然に伝わる発信」が必要だと感じました。
実際、SNSを活用して成果を出している士業の方もいます。そういった方を見ると、継続的な発信や、読んでくれる人に対する工夫がしっかりしていて、単なる宣伝ではなく“信頼の蓄積”を丁寧に行っている印象です。
私はSNS営業には本格的に取り組んでいませんが、だからこそ感じるのは、「SNSは即効性を期待するものではない」ということ。今後もし活用するなら、「集客のため」というよりも、「自分のスタンスや想いを伝える場所」として、少しずつ向き合っていくのがいいのかなと考えています。
ホームページ:2年間反応ゼロから年2件の契約獲得へ
ホームページについてお話しします。今では社労士でもホームページを持つのが当たり前になっていますが、実際に集客につながっている人は、そこまで多くないのが実情ではないでしょうか。
私自身、開業直後にホームページを立ち上げたものの、最初の2年間はまったく反応がありませんでした。正直、「やっぱりホームページって意味ないのかな」と思ったこともあります。
ただ、それでも私はページの更新を続けました。というのも、私の営業スタイルは「地域密着」。ターゲットは基本的に市内の中小零細企業に絞っています。だからこそ、ホームページも「広く全国に発信する」のではなく、“地元の誰かが検索したときにヒットするページ”を意識して作っていたのです。
たとえば、事務所紹介の中でも「〇〇市で活動する社労士です」と地域名をしっかり明記したり、「〇〇市 就業規則」「〇〇市 労務相談」など、地元の方が検索しそうなキーワードを自然に含めるよう工夫しました。また、労務ニュースの更新なども地道に積み重ねました。
すると、ある日突然、一本の電話が。「ホームページを見たのですが、顧問社労士を探していて…」という、まさに地域の企業からの問い合わせでした。そこから少しずつ反応が出始め、今では地元の企業から年間2件ほど、ホームページ経由で契約につながっています。
たしかに即効性のある営業手段ではありませんが、「信頼感のある窓口」として、コツコツ育てていけば成果が出る媒体だと実感しています。
紹介:開業2年はゼロでも、いずれ最強の営業ルートに
最後に「紹介」についてお話しします。開業から14年が経った今、私にとって最も多くの契約につながっているのが、実はこの「紹介」経由です。
紹介のルートは大きく2つあります。ひとつは、既存のお客様からのご紹介。もうひとつは、税理士など他士業の方からの紹介です。最近では、地元の商工会議所や法人会を通じて知り合った先生方からのご紹介も増えてきました。
私が税理士の先生などとつながるようになったのは、名刺交換する際「何かあれば電話でも気軽に聞いてください」と、無償で労務の相談に応じていたことがきっかけでした。
「無料で、こんな質問しても大丈夫ですか?」と遠慮がちに聞かれることもありましたが、私は特に線を引かず、「せっかくご縁があったのだから」と丁寧に答えるようにしていました。そうした対応を続けているうちに、「じゃあ、うちのお客さんで困ってる人がいるから紹介してもいいですか?」という流れが自然と生まれてきたのです。
つまり、「まずはこちらが先に役に立つ」ことで信頼を得て、それが紹介という形で返ってきたのだと思います。
紹介には他の営業手法にはない強みがあります。紹介者がすでに信頼の橋渡しをしてくれているため、お客様との関係構築が圧倒的にスムーズです。実際、「○○先生の紹介なら安心です」と最初から信頼して相談してくださるケースも多く、契約にもつながりやすいと感じます。
その反面、紹介にはプレッシャーもあります。紹介してくれた人の顔をつぶせない、という意識が働きますから、普段以上にお客様に満足してもらえるよう、対応にもより一層気を配る必要があります。
こうした紹介の流れは、開業直後からいきなり得られるものではありません。私自身も、開業して最初の2年間は紹介経由の契約はゼロでした。実績も人脈も少ないうちは、紹介が回ってくることはほとんどありません。地道に仕事をこなしながら、「この人なら安心」と思ってもらえる関係を築いていくことが大切です。
一度紹介のサイクルが回り始めると、それは大きな財産になります。丁寧に対応すれば、紹介されたお客様がまた別の方を紹介してくださるという良い連鎖が生まれます。結果として、自分から営業をかける回数が減っていき、自然と顧客がつながっていく流れができていきます。
紹介は、まさに「信頼」の延長線上にある営業ルートです。目先の契約を急がず、誠実に積み重ねていけば、やがて最強の集客手段になると私は実感しています。
まとめ
ここまで、いろんな営業のやり方を紹介してきました。社労士が仕事を取っていく方法って、本当にいろいろありますよね。でも、大事なのは「自分に合うやり方」を見つけることだと思います。
全部やろうとしなくて大丈夫です。まずは、「これならやってみてもいいかも」と思えるものから、気楽に始めてみるのがいいんじゃないでしょうか。
たとえば、飛び込み営業とかテレアポは、正直メンタルきついです。断られて当たり前。でも、それでもやってる人もいます。
異業種交流会なんかは、一回出ただけじゃ何も起きないけど、同じ人たちと何度か顔を合わせてるうちに、少しずつつながりができてきます。
SNSやホームページは、すぐには効果出ないけど、自分を知ってもらう「入り口」としてはアリだと思います。
そして、やっぱり一番ありがたいのは「紹介」。これは本当に強いです。紹介から紹介へってつながっていくと、自分から営業しなくても、自然と仕事が広がっていきます。
最初は何をやっても手応えがなくて、つらい時期もあります。でも、そういうのをコツコツ続けた先に、ちょっとずつ道が見えてくるもんです。今うまくやってる人も、最初はみんな同じだったと思います。
だから、焦らず、できそうなことからちょっとずつ。無理なく、自分のペースでいきましょう。
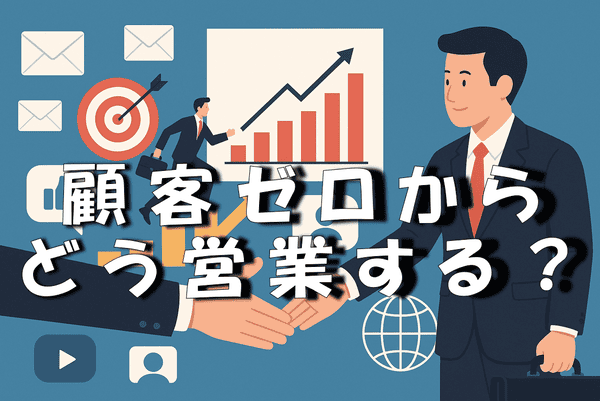


コメント