社労士として独立を考えたとき、「まず何から始めればいいのだろう?」と手が止まってしまうことはありませんか?私自身も開業を前に、やることの多さに戸惑った経験があります。
この記事では、開業14年の経験をもとに、独立前に準備しておきたい4つのポイントをまとめました。事務所名やキャッチコピー、業務案内の作成、営業トークの工夫など、実際に役立つ内容ばかりです。
これから一歩を踏み出す方が、少しでも安心して準備を進められるヒントになれば嬉しいです。
事務所名をしっかり考える
準備で大切なことの一つ目は、事務所名を決めることです。事務所名についてはいろいろな意見があると思います。私が開業した当時、色々調べて得た情報では、例えば「あ」から始める事業所が50音順のリストでは上位になるからよいだとか、カタカナを使ったこった名前が良いとか、いろいろな情報がありました。
私自身の経験から申しますと、事務所名考えるときのポイントとしては、はじめは「社会保険労務士」または「社労士」という言葉を入れた事務所名にしたほうがいいということです。営業をするにしても、名刺交換をするにしても、「社会保険労務士」や「社労士」という言葉が入っていれば、何をしているのか説明もしやすいです。
同じ社労士県会の同期開業の社労士の中には、屋号だけでは何をしているかわからないような、かなり凝ったカタカナの事務所名を付けた社労士もいました。「社会保険労務士の事務所です」ということが名前で分からないと、まずそこから説明する必要がありますし、その前に怪しまれて話を聞いてもらえないこともあります。仕事が分かりやすいということが、最初は大事なんです。
事務所の特徴を整理し、キャッチコピーを考える
2つ目に考えておいていただきたいのは、事務所の特徴と、キャッチコピーです。例えば「社会保険労務士○○事務所」や「○○社労士事務所」と氏名や地名でつける場合でも、「何ができるのか」や、ほかの社労士事務所と比べて「どういう特徴があるのか」というキャッチコピーをつけるのです。そのキャッチコピーを、一言か二言、15秒ぐらいで話せるかどうかで特徴を覚えてもらえる可能性がぐっと上がります。
事務所の特徴を考える
特徴をコンパクトにまとめるときのコツとしては、3つから5つに絞って箇条書きにすること。それは自分のやりたいことだけにしてはダメで、お客様の問題を解決できる内容にしなければなりません。皆さんはご自分の事情や経験、特徴に合わせて考えてほしいのですが、例えば私などは、開業時に次のような特徴を掲げました。
上記の「地域密着の社労士であること」に関しては、同じエリアでは、もっと広いエリアで活動している社労士が多かったので、経験も知名度も豊富な大手事務所や先輩社労士と同じ土俵で戦うのではなく、より身近で顔の見える関係を築ける「接近戦」でこそ、自分の強みが活きると考えたのでした。
そこで「○○市に限定して顧問活動をしています。」というような感じで具体的に特徴を出すことにしたのです。
その地域密着のメリットとしては、何か労務トラブルなどがあったときに事務所所長(代表)が直接駆けつけますと説明するのです。大きな事務所では所長が来ることは少ないから、開業して間がなく、時間があることを逆手にとりました。
「社員研修が得意」ということに関しては、お客様がパワハラで困っていたら、私(社労士)が御社の状況に合わせてカスタムメイドのハラスメント防止研修を行います。というような説明をしました。
また、私は勤務社労士時代に、新卒、中途の採用担当や、社内研修の講師も行っていましたから、特徴に社員研修や採用のアドバイスができることを加えました。
特徴と説明は具体的なほどいいと思います。たとえば「人的資源管理(ヒューマンリソースマネジメント)で日本を元気にします」って言っても、これではイメージがわきません。だってその人的資源管理で日本を元気にしても、お客さんの社長さんにとってメリットが具体的にわからないからです。だからあまり意味が伝わらないんですね。
自社の強みというのは、自分の事務所が他の労務士事務所より強い点など、独自の特徴だけではありません。そうではなくて、お客さんが望んでいること、お客さんのニーズ、お客さんが求める価値なのです。そのお客さんが求める価値が他よりも明確に優れていることが強みなんです。
この特徴に関しては、実際に皆さんの経験や事務所のコンセプトに応じて独自に作成します。私は地域密着で所長(代表)が直接駆け付けることを開業当初の特徴にしていましたが、今はZOOMなどを活用してエリアを選ばず、顧問活動を行うという特徴でもいいかもしれません。
例えば給料計算が正確だとか、助成金が強いとか、対応できる助成金の種類が多いなど、労働時間に特化するのでも、残業の管理だったり、生産性を上げて利益をアップするでも何でもいいのです。
特徴をもとにキャッチコピーを作成する
そしてその特徴の中から、特に一番強調したいことをキャッチコピーとして決めるのです。私の場合は「○○市の地域密着の社会保険労務士事務所です!」というキャッチコピーにしました。
その理由は、ほかの特徴に比べて、フットワークが軽くてすぐにお客様のところに駆け付ける、という点には自信があったからです。新人社労士にとって、これは経験や実力がなくでも実行できることでした。
特徴は、随時少しずつ入れ替えたりして、それで、「お客さん興味持ってくれたかな」とか「どうかな」ということで修正していってください。事務所名と事務所のキャッチコピー、強み、特徴として、言えることを用意していきましょう。
開業にあたって、自分の特徴と、その特徴によるお客様のメリットが説明できないと、苦労するんですね。社労士の登録者は約4万4千人もいるのです。今後、開業社労士も、法人の勤務社労士も増えてくる中、あなたが開業しようと思うと、やっぱり自分の特徴を言えることがすごく大切になります。
業務案内(メニューリスト)を作ろう
3つ目のポイントは、業務案内(メニューリスト)を用意しておくことです。先に考えた事務所の特徴をふまえて、「うちではこんなことができますよ」という一覧を作っておくイメージですね。実はこれ、あるのとないのとでは営業のしやすさが全然違います。
メニューリストの具体例です。
- 顧問契約で対応する業務(料金表も一緒に用意しておくと便利)
- 労務相談対応(労働時間、残業、休職、解雇など)
- 採用・退職・労働条件変更等の実務アドバイス
- 社会保険・労働保険の各種手続代行
- 雇用契約書・労使協定書等の作成・整備
- 法改正情報の提供と対応支援
- 労務リスクチェック
- 顧問契約以外の業務(別途料金がかかる場合は金額も明記)
- 就業規則の新規作成・改定
- 助成金申請
- 人事労務関連のセミナーや社内研修
- 給与計算代行
- 人事評価制度の導入支援
お客さんが知りたいのはシンプルで、「この事務所は何をしてくれるの?」「自分の悩みは解決できるの?」ということなんです。そんなときにメニュー表があると、パッと見て内容も費用感も伝わるし、こちらとしても説明がぐっと楽になります。
もちろん、その場で見積書を作る方法もありますが、いちいち事務所に戻ってから準備するのは時間も手間もかかりますよね。お客さんにとっても、リストを見てすぐにイメージできる方が安心です。だからこそ、提供できるサービスを整理して形にしておくのは大事なんです。
そして実際に興味を持ってもらえたら、「このサービスがあなたの悩みをこう解決しますよ」と伝えてあげましょう。
たとえば給与計算なら、「もう細かい計算や法改正に悩まなくて大丈夫です。従業員からのクレームや小さなミスもなくなるので、安心して任せていただけます」といった具合です。そのうえで「料金はこのくらいです」と案内すると、納得感も持ってもらいやすいですよね。
就業規則の作成、手続き代行、求人票の作成、有給休暇の管理、働き方改革の提案、同一労働同一賃金、助成金の申請、どれも同じです。
まずは「いま自分ができること」をまとめてスタートしてみましょう。経験を積んでできることが増えたら、その都度メニューを追加していけばいいのです。そうやって少しずつリストを育てていくと、結果は大きく変わってきます。
セールスの力をつける(セールストークの準備)
4つ目に大切なのは、やっぱりセールス(営業)の力なのです。これはとても大切なので、私は開業される方はセールストークについてきちんと勉強するのがいいと思っています。セールストークというと説明することだって思いがちですが、違うのです。
説明をするのではなく、セールストークというのは、お客様にどんな質問を投げかけるかということ、お客さんにどんな質問を投げかけて、どういう悩みとか望みを教えていただくかということなのです。それでどういう方向で解決していきたいのか、そういうことを聞き出すのが、セールストークなのです。
就業規則を作りたいというお客がいた場合、「当事務所では○○万円で作成します。」ではなく、「どのようなきっかけで就業規則しようと思ったのですか?」と質問します。その理由が助成金の申請に添付するために作成の必要があるとか、社内の風紀が乱れていて服務規律を整備したいなど、理由によってどこに重点を置いて規則を作成するのか全く変わってきます。
また、ハラスメント研修を行いたい、といった場合では、なぜその研修を行いたいと思ったのかを聞きます。単に今世間で話題になっていそうだから、という理由であれば広く一般的な事柄を網羅した研修になるし、実際に社内で問題が起きていて、改善しなければならないことが具体的にあるというケースでは、その問題を解決できるような研修を提案するのです。
目的を聞いたうえで、問題を解決できるメニューを業務案内で提案すれば簡単にセールスの力がアップして、お客様と契約できるようになっていきます。
まとめ
社労士としての開業を成功させるためには、次の4つの準備が非常に重要です。
- 事務所名をしっかり考える
- 事務所の特徴を明確にしてキャッチコピーを作成する
- サービスをリスト化し、業務案内を整備する
- セールストークを準備し、ニーズに応じた提案力を高める
これらをしっかり準備しておくことで、営業活動が格段に楽になり、年収アップにも直結していきます。結局、開業を成功させるには、地道な準備が重要だったと私は何度も実感してきました。焦らず、着実に、一歩ずつ積み上げていきましょう。

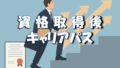

コメント